台風や大雨により発生した廃棄物(災害ごみ)の処理に関係各位がご苦労をされているようです。
あらためてお見舞い申し上げます。
日経新聞HP2019.10.14より転記
大規模な浸水被害をもたらした台風19号による「災害ごみ」が、各地で山積みになっている。ごみの総量は西日本豪雨の190万トンを超える見通しで、処理に数年かかるとみられる。環境省が各自治体に求めていた「災害廃棄物処理計画」を策定していた市町村は全国で3割に満たず、災害ごみに対する備えの遅れも浮かび上がる。
「災害ごみ」という言葉は法律上のものではないため、どう処理するかについて廃棄物処理法で定義される一般廃棄物もしくは産業廃棄物のどちらかに区分されることになります。
ここで廃棄物処理法における区分のしかたをみてみます。
1.固形状または液状の不要なもので土砂は除く
2.事業活動によって生じる廃プラスチック、金属くずなど産業廃棄物に分類
3.2以外の廃棄物が一般廃棄物となり、ゴミとし尿に分類される
4.一般廃棄物は家庭と事業系に分かれる
5.毒性・感染性など危険性の高い特別管理産業廃棄物がある
災害により直接発生した廃棄物は事業所から出ていても事業活動によらなければ一般廃棄物にあたるという判断になりそうです。被災後の復旧活動により発生する産業廃棄物との区分が難しそうですし、さらに 家庭からなのか事業所からなのかの区分がそもそも難しそうです。
参考:長野市HP「台風19号により発生した災害ごみの出し方」
https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kateigomi/439071.html
政府は2018年に「産業廃棄物対策指針」を定めています。
環境省HPより抜粋 http://kouikishori.env.go.jp/guidance/guideline/
・・・本指針は、災害廃棄物の処理に当たっては、まず住民の健康への配慮や安全の確保、衛生や環境面での安全・安心のための迅速な対応が必要であるとともに、分別、選別、再生利用などによる減量化も必要であることから、発生した災害廃棄物の処理において実用的な技術情報を盛り込み、被災した地方公共団体だけでなく、支援する地方公共団体にとっても実用的な指針とすることを目指して策定している。本指針を参考に、地方公共団体が平時からの一般廃棄物処理システムも考慮しつつ、実際に災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理することができる災害廃棄物処理計画を策定・改定するとともに、災害廃棄物対策に関する教育訓練や人材育成にも努めることが期待される。
いずれにしても被災地の皆様の生活が一日も早く安定されることをお祈りいたします。

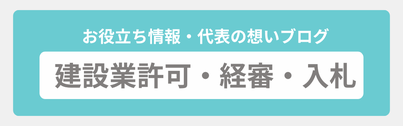
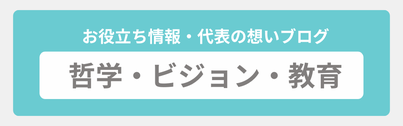
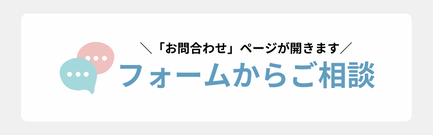
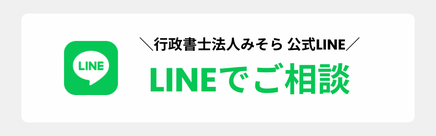



コメントをお書きください