先月後半から経済活動が再開されてきて、また浜松市については例年7月末から8月頭にかけて農振除外(農用地利用計画変更申し出)の受付期間があるため、この時期は建設・不動産関係のお取引先様からのお問い合わせが重なります。
ところで他県の同業者の方たちと情報交換をする際に、私の地元では農地転用の仕事の割合が多いという話をすると、結構おどろかれます。農地転用に深く関係する法律(農地法、農振法、都市計画法など)は日本全国、どこでも適用される共通のルールです。それなのにどうして仕事量の偏りがあるのか、常々、疑問に感じていますが、ひとつは次のような浜松市の歴史的な特徴があるからなのではと思っています。
現在、浜松市は政令指定都市のひとつで80万人弱の市民が暮らしていますが、面積については岐阜県高山市に次いで2番目の広さを誇ります。1911年に浜松市が誕生してから1991年までの80年間で周辺の村や町と合併を重ねて旧浜松市の形が出来上がり、2005年に周辺11市町と合併して、現在の浜松市が誕生しました。
浜松市の合併の変遷
http://www.hamamatsu-books.jp/alacarte/detail/4.html
中心地に集まる人口が増えていくのと同時に、もともと村々に集落があったため、合併を重ねるごとに郊外に住む人口の割合も高くなっていったと思われます。現在では、市街化調整区域内に居住する人口は30パーセント程になっています。80÷30で約24万人です。自慢して良いのか分かりませんが、ちょっとこれは凄い数字だと思います。このパワーが市街化調整区域内の農地転用を生み出してきたのだと思います。
ちなみにお隣の政令市である静岡市の資料を見てみますと、およそ10パーセントが市街化調整区域内に居住しているようです。
浜松市都市計画マスタープラン(p11)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/toshikei/city/tosike/masterplan/documents/mp1.pdf
市街化調整区域内で育ち、家庭を持ち、次の世代を育てていくという過程の中でまた市街化調整区域内に住宅を新築したいというニーズが発生します。これには郊外に若い社会人の職場となる、大きな製造業の事業所が存在していることも影響をしていると思います。
居職近接、自宅と会社をドアツードアで、マイカーで移動するのが、浜松の常識です。浜松市ではこうしたニーズをくみ取るための施策を運用してきました。
大規模既存集落内の自己用住宅
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/daikibo.html
では、今後の施策はどうなっていくのかという疑問がありますが、やはり人口が減少をし始めている状況では、市街化調整区域内での開発をより緩和していくということは考えにくいです。
浜松市HPでも次のようなQ&Aが掲載されています。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/square/room/opinion/toshikekaku/2016-1581.html

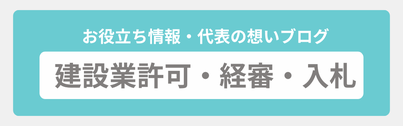
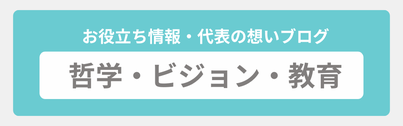
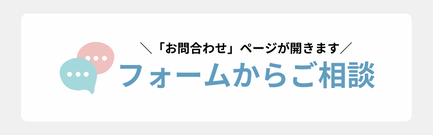
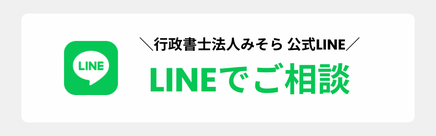



コメントをお書きください