
※令和5年4月に改正農地法が施行されました。
俗に「農家資格」といわれる、農地の取得を農業委員会に申請するにあたり、前提となる農業の経営面積(自作・小作の両方)の規制が撤廃されました。
経営面積は既にその方が農地を所有または借り受けて耕作をしている面積のことで、地域により最低の面積は3反(たん)以上、5反以上など様々でした。
1反の面積は約1000平方メートルとかなり広く、50メートルプールより少し狭いくらいのイメージです。
農業のノウハウを習得し、設備や機械を導入し、作業の時間をかけないと、3反を管理することも容易にはできません。
こうして農地の取得への新規の参入をこれまで規制していた訳です。
しかし令和5年4月からの最低の経営面積の規制の撤廃により、いままで農業を経営したことのない方にも農地を取得する機会が広がっています。
例えば、これまで一切、農業をしたことがないサラリーマンの方が、自宅の隣にある小さな畑だけ取得して耕作をしたい場合などです。
取得を希望する農地が小さければ、かける時間と労力、道具や肥料等の購入資金、栽培のノウハウも少なくて済みます。
審査する農業委員会も、その方がしっかりと農地を管理してくれるかどうかを懸念する程度が小さくなりますので、まずは小さな農地からチャレンジするのが良いでしょう。
経営するといっても、お店に卸して販売するレベルになく、自家消費(収穫したものを自宅で食べたり、友人知人に配るだけ)でも構わない、と判断される農業委員会が多いのではないかと思います。
大事なことは上手に栽培することよりも、取得した農地を荒らさず、また周りの農地や宅地に迷惑をかけないよう管理する、ということだと思います。
最新の情報は、取得を検討されている農地が所在する市町村の農業委員会事務局にご確認ください。書面審査のみであったり、実績の確認をしてから、という規制があったりと様々です。
以下のご説明は令和5年4月に改正される前の扱いです。
規制は撤廃されましたが、農地取得の許可申請(農地法3条)をする際には、農業員会で審査されることには変わりありません。
審査を受けるうえでの注意点は、これまでの考え方が参考になると思います。
---------------------------------------------------------------------------------------------
浜松市内で2名のお客様から農家資格を得て農地を取得したいという相談を受けています。元々が農家の方でない場合には、いわゆる農家資格を得なければなりません。農家資格があるということは、市の農地台帳に記載があることが前提として必要です。
農地台帳は農地を経営している面積が、合計して1000平方メートル以上、借りるか、所有している世帯について、住民基本台帳と固定資産台帳をもとに作成されます。
また作成された農家台帳は毎年、各世帯に現況確認の通知が届きます。
「この畑ではこれを作っているよ」
「農機具はこんなものがあるよ」
というような回答を市の農業委員会事務局に対してします。
この農家台帳をもとに農家資格の判断がされますので、経営管理している農地を荒らしてしまっていたり、別の用途に無断で転用してしまっていたりすると、新しく農地を取得するのにふさわしくない、という判断がされます。農地を取得しようとする場合には、世帯員の農業従事日数は年間で60日以上、世帯合計で150日以上でなければなりません。
そして農地取得後の経営面積が最低でもこれだけ必要、という基準があります。これは地区ごとに数値が異なりますので注意が必要です。浜松市では以下のようの定められています。
中区、東区、南区、西区(舞阪)、天竜区 ・・・ 20アール
浜北区、西区(舞阪以外)、北区(都田町、・・・ 30アール
新都田、三方原)
北区(細江、引佐) ・・・ 40アール
北区(三ケ日) ・・・ 50アール
※上記の最新情報は浜松市ホームページからご確認ください。
新規就農には、こうした手続き上の課題もありますが、それよりも農業という実務のノウハウを習得しなければなりません。地元の農家さんや知人、親族に相談しながら、計画を進めていってください。新規就農の見通しが立ってきたら、農業委員会に相談することになります。一年か一年半ぐらいのスパンで計画をたてていくのがよろしいかと思います。
お問い合わせ

みそらでは建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。

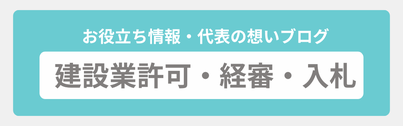
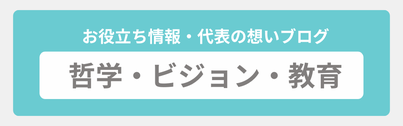
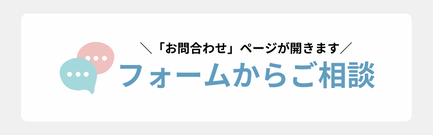
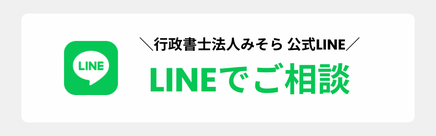



コメントをお書きください