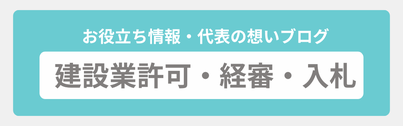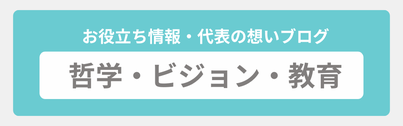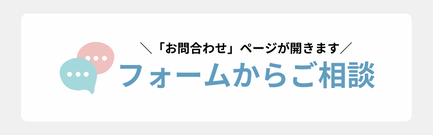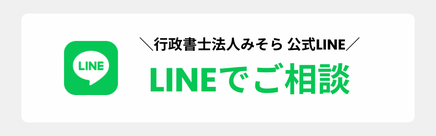最近、機械器具設置工事業のお客さまからのご相談が続いています。機械器具設置工事は建設業法で定める29業種のうちのひとつであり、機械器具メーカー、卸売り商社、施工会社などが許可を持っています。
こうしたお客様にとっての共通の課題の一つは、建設業法で求められる専任技術者、主任技術者、監理技術者の確保です。建設業法に則った事業の運営は、コンプライアンス上のみに限らず、営業、入札、契約など取引活動において欠かせないことです。
ところで、どのような工事が機械器具設置工事に該当するのか、という疑問がありますが、国は次のように規定をしています。
旧建設省の告示
機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を設置する工事
国土交通省ガイドライン
・プラント設備工事
・運搬機器設置工事
・内燃力発電設備工事
・集塵機器設置工事
・吸排気機器設置工事
・揚排水機器設置工事
・ダム用仮設備工事
・遊戯施設設置工事
・舞台装置設置工事
・サイロ設置工事
・立体駐車設備工事
機械器具設置というイメージから、私たちはもっと広い範囲の機械器具が該当するのでは、と考えてしまうところですが、上記のように国はかなり限定的に列挙しています。
会社側としては機械器具設置工事として取引をしていても、国や都道府県の考えでは、電気工事、管工事、電気通信工事、とび・土工工事業に該当する、というケースが生じてきてしまうのです。
こうした解釈の相違があったとしても、普段の取引上では支障が生じることは無いかもしれませんが、危惧されるのは建設業法上の技術者です。
特に建設業許可を維持する上で、必ず営業所に一名は必要となる専任技術者、この役職について、交代の必要性が生じた際に課題となるのです。専任技術者となっている方の引退、定年、退職の場面です。
機械器具設置工事に対応する資格は「技術士」しか規定されていませんので、多くの会社様は実務経験を証明して建設業許可を維持するほかありません。
そして実務経験を証明しようとする際に、上記の国が定めたガイドラインが重くのしかかることになるのです。画期的な解決方法はありませんので、過去の資料を細かく見直しながら、行政庁が納得する証明材料を整えていく作業が必要になります。
ただ替わりとなる人材が会社に存在しなければ、手の打ちようがありません。そういう意味で、5年、10年スパンでの対策が求められるのです。