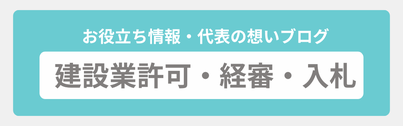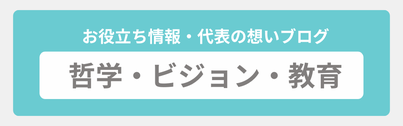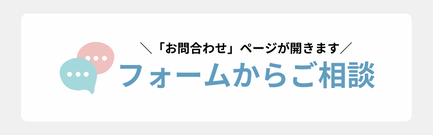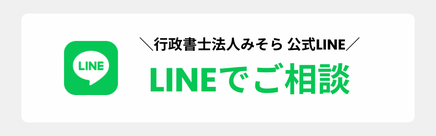いよいよ退職への動きです。
きりの良いところで3月末退職と決めて、所長に切り出しました。
最初はあまり前向きには受け取ってもらえなかったと思います。
この業界は、一部の事務所以外は組織的に業務ができていません。
属人的ですから、従業員がひとり欠けるだけでダメージを受けます。
それとやはり土地柄、司法書士、土地家屋調査士のオプションとして行政書士業務をやられている方がメインでした。
取り扱う内容も、農地法や都市計画法などの土地関係に限ります。
私がお世話になった事務所もそういうやり方でした。
地方の小さな街ではその方が理にかなっていると思います。
「行政書士だけじゃ(食っていくのは)難しいぞ。」所長からの忠告はごもっともですが、東京の行政書士、丸山学さんの
著作を読んで、やれると思い込んでいましたから、食い下がりました。
受験勉強中、特に合格したことが分かってから、自分の中に沸々と湧き上がってきた気持ちを、抑えることなんて出来ません。
「自分という人間がどれだけ世間に役立つのか、試したいです。」口頭では言い負けてしまうので、所長あての手紙にしたためました。それでようやく諦めていただきました。
こういう気持ちって、本来は二十歳の頃に芽生えているのが、男として健全だと思うのですが、私は30歳を過ぎてからでした。
なので、若い方の「社会に出ても、なにしていいかわからないよ」という気持ちは、オッサンの割に分かる方だと思います。
「行政書士だけじゃ(食っていくのは)難しいぞ。」
退職の目途は立ちましたが、この忠告との戦いは始まったばかり、スタートラインに立っただけ、ということはその時の自分には分かっていませんでした。
今思えば「自分の力を試したい」というのも身勝手な思い込みです。当時、行政書士法が出来てから約50年経過していました。ということは、先人が積み重ねた、行政書士への50年分の信用が世間に蓄積されているということです。
畑でいえば、先人が耕して、種をまいて、草刈りをして、水やりをして大きく育ったところを、収穫だけするようなものです。
所長の口癖のひとつ「俺たちは50点からスタートしている」の意味が独立してから、だんだんと身に染みるようになります。
ちなみに開業後はなかなか顔を出しづらいものですが、所長への義理は、 年賀状や挨拶など何らかの形で、絶やさないように気を付けました。