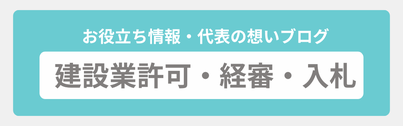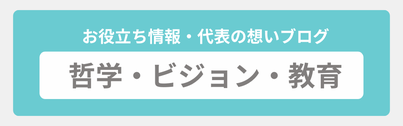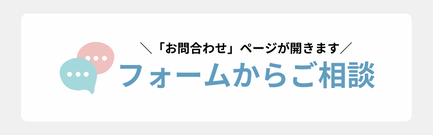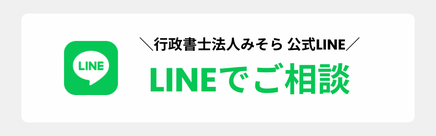今月1日より施行された静岡県盛土等の規制に関する条例(盛り土条例)の説明会で聞き取った概要をお知らせします。
県庁の担当者も手探りの状況であるため、今後もまめに情報チェックしていく必要があります。
※変更や訂正がありましたら改めてご案内いたします。
まず「盛り土」という言葉のイメージや昨年、熱海市伊豆山で起きた災害から、谷や斜面に大規模に土砂を埋め立てる行為を規制するように思われる方がいらっしゃるかもしれません。
首都圏から県内に持ち込まれた残土が、県東部の山中に埋め立てられる、そんなイメージです。
しかし実際のところは、平たんな地形も対象になっています。例えば市街地に残った田んぼを道路と同じ高さに埋め立てる行為も対象です。また市街化区域、市街化調整区域、非線引きの用途地域、用途無指定の地域、そのような都市計画法上の区域に規制の違いはありません。
盛り土する面積が1,000㎡または土量が1,000㎥以上であれば対象です。
次に盛り土に使用する「土砂等」の定義です。
土砂及び土砂に混入し、又は付着した物、改良土並びに再生土
改良土・・・土砂にセメントや石灰等の改良材を混合し安定処理された物
再生土・・・産業廃棄物が適正に処理され、土砂と同様の形状を有する物
というように、山土以外にも土工事に使用される様々な資材が該当します。
そのうえで、規制の「盛り土」にならない行為にはどのようなケースが考えられるのかが、次のように例示されています。
・敷き均し(平坦地で深さ30cm未満)
・道路承認工事、道路占用工事、河川占用工事
・構造物の設置に伴う埋め戻し
・田んぼや畑の畝、畦の補修
・盛り土・切り土がある場合の切り土の部分
・面積1,000平米未満かつ土量1,000立米未満の造成
・7月1日の時点ですでに他法令の許認可を受けている場合
→許可等を受けた範囲内で許可等がされた期間内に行う行為
もし条例の許可を取るとした場合に必要な日数としては、測量調査、土壌汚染の調査、地元住民への事前説明会に書類審査、準備も含めれば最低でも半年以上は見ておかなければならないと思います。
また他法令の手続との前後関係について、県の側は指定していませんが市町の側で、先に盛土条例の許可を取るよう、今後、指導をかけてくることも予想されます。
関係者が皆、不慣れな状況ですので、相当長く見ておく必要があると私は感じております。
最後に、本条例の情報入手先および担当部署は次のとおりです。気になることがあれば、こまめに確認をして頂きたいと思います。人員が限られた中で、県下全域の対応を迫られているようですので、なるべくメールでの問い合わせが良いようです。