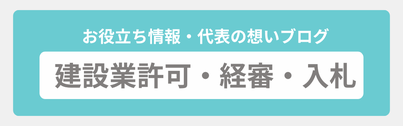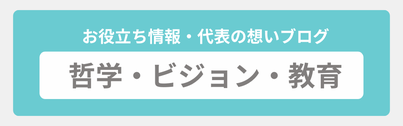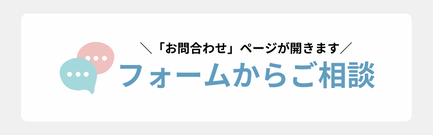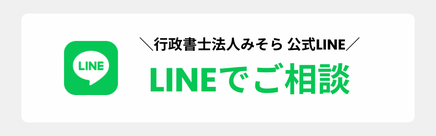目次
■産業廃棄物処理振興センターの講習申し込み
■廃棄物処理の基本知識
■経営的基礎とは
産業廃棄物処理振興センターの講習会の申し込み

令和6年度(2024年4月~2025年3月)に開催される、産廃許可申請に関する講習会について、産業廃棄物処理振興センターが実施をしています。
2024年度も昨年同様、事前にインターネット上で講義ビデオを視聴して受講し、会場で修了試験を受けるオンライン形式講習会と会場で講義を受け講義後に試験を受ける対面形式講習会を実施しています。
開催形式により受講料が異なりますので、お申込みの際はご注意ください。
講習会の日程について
本講習は、産廃の収集運搬業の許可申請をする方が申請する前に受講し、申請をする際には「受講証」の写しを提出しなければなりません。また受講日の当日に受講証は交付されません。よって許可申請をしようとする1か月前(遅くとも3週間前)までに済ませておくことが安全です。
受講をするのは、個人事業者であれば事業主、法人であれば役員であることが求められています。例外として使用人(法令に則り権限を与えられた者)が受講することも認められてはいますが、安易に運用すると法令違反の元になりますので、事業主又は役員が受講、としておきましょう。
建設工事業者が収集運搬業の許可を持たずして現場から産廃を搬出し処分場へ搬入できないのは、下請負人として現場に出入りしているケースです。
これがもし元請負人の場合には、発注者と同じ排出事業者責任を負っており、収集運搬の許可を持たずしても産廃を収集運搬することができます。
申込から修了証を取得するまでの流れ

(1)お申し込み
申請はWebのみとなります。講習の課程・試験の日時・会場を選択し、申込をします。
(2)受講料のお支払い
受講料のお支払いが完了しますと受講決定のお知らせメールが届きます。
(3)講義を受講
◆オンライン形式の場合は受講決定のメールの後、2週間程度でテキスト等の資料が届きます。マイページにログインをして講義動画を視聴し受講します。
◆対面形式の場合はお申し込み時に指定した日時に会場で受講します。テキストは会場で配布されます。
(4)試験を受ける
◆オンライン形式の場合はお申込み時に指定した日時に会場で試験を受けます。受験についての留意事項等はテキストと一緒に届きますのでご確認ください。
◆対面形式の場合は講義の終了後、引き続き同じ会場で試験を受けます。
(5)試験結果の受け取り
試験に合格した方には修了証が交付されます。不合格に方には再試験のご案内が届きます。マイページにログインすると合否の確認ができます。
お困りの方はフォームからお問い合わせください。
みそらでは建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。

廃棄物処理の基本知識

建設工事等に伴って生ずる廃棄物には次のような特殊性があります。
「廃棄物の発生場所が一定しない」
「発生量が膨大」
「廃棄物の種類が膨大であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別することにより再生利用が可能なものが多い」
「廃棄物を取り扱うものが多数存在する」
建設廃棄物は不適正処理の事例として取り上げられるものが多く、とりわけ、木くず、がれき類等解体廃棄物については不法投棄量が多く、生活環境保全上の大きな問題となっています。
建設廃棄物の適正処理を図るためには、排出事業者においては、建設廃棄物の発生抑制、再生利用、減量化等その他適正処理のため排出事業者としての責任を果たすとともに、発注者等の排出事業者以外の関係者においても、それぞれの立場に応じた責務を果たすことが重要です。
排出事業者の責務と役割について

~排出事業者について~
建設工事では、原則として元請業者が排出事業者に該当します。建設工事では「建設工事等の発注者」、「発注者から建設工事等を直接請け負った元請業者」、「元請業者から建設工事等を請け負った下請業者等関係者」など、関係者が多数いることから、廃棄物処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがあります。そのため建設廃棄物については、実際の工事の施工を下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者として処理責任を負わせることとしています。
~建設廃棄物の減量化について~
排出事業者は、建設廃棄物の発生抑制、再生利用等による減量化、再生資材の活用を積極的に図らなければなりません。
~自己処理について~
排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処理になければなりません。排出事業者が自ら行う運搬、中間処理(再生も含みます)、最終処分をいい、それぞれ廃棄物処理法に定める基準に従い処分をしなければなりません。
~委託処理について~
排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、廃棄物処理法に定める委託基準に従い、「収集運搬業者」、「中間処理業者」、「最終処分業者」とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行い、適正な処理費用の支払い等、排出事業者として適正な処理を確保しなければなりません。また、現場内で行う処理であっても、下請業者に処理させる場合は、委託処理に該当します。
発注者等の関係者の責務と役割

建設工事等における発注者等の排出事業者以外の関係者は、「発生抑制」、「再生利用等」による減量化を含めた適正処分について、排出事業者が廃棄物処理の責任を果たせるように、それぞれの立場に応じた責務を果たさなければなりません。
■発注者は、廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努めるとともに廃棄物処理の条件を明示する。
■設計者は、発注者の意向をふまえ、廃棄物の発生抑制、再生利用を考慮した設計に努める。
■下請け業者は、廃棄物の発生抑制、再生利用に関し排出事業者に協力する。
■処理業者は、排出事業者との書面による委託契約に従い、廃棄物を適正に処理する。
■製造事業者(メーカー)は、梱包を簡素化するなど、廃棄物の発生抑制に努めるとともに、製品が廃棄物となった場合、適正処理が困難にならないように製品開発に努める。
建設廃棄物の種類

建設廃棄物には、直接工事から排出される廃棄物と建設現場や現場事務所などから排出される廃棄物があります。排出事業者は、自らの責任において建設工事等から排出される産業廃棄物を、その種類に応じた処理基準に従い適正に処理しなければなりません。建設現場や現場事務所などから排出される一般廃棄物の処理については、廃棄物は生じた区域における市町村の指示に従い処理しなければなりません。
~一般廃棄物~
現場事務所などから排出される生ごみ、新聞、雑誌など
~産業廃棄物~
①廃プラスチック類
→廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類
②ゴムくず
→天然ゴムくず
③金属くず
→鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず
④ガラスくず・陶磁器くず
→ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくず
⑤がれき類
→工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物(コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片)
⑥汚泥
→含水率が高く微細な泥状の掘削物(掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/㎡以下または一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下)具体的には場所打杭工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水)
⑦木くず
→工作物の新築、改築、除去に伴って生ずる木くず(型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、抜根・伐採材、木造解体材等)
⑧紙くず
→工作物の新築、改築、除去に伴って生ずる紙くず(梱包材、段ボール、壁紙くず等)
⑨繊維くず
→工作物の新築、改築、除去に伴って生ずる繊維くず(廃ウエス、縄、ロープ類)
⑩廃油
→防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ(タールピッチ類)
※⓵から⑤は安定型最終処分場に持ち込みが可能な品目。ただし石膏ボード、廃ブラウン管の側面部(以上ガラスくず、陶磁器くず)、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板(以上金属くず)、廃プリント電線板(廃プラスチック類、金属くず)、廃容器包装(廃プラスチック類、ガラスくず、陶磁器くず、金属くず)は除く
~特別管理産業廃棄物~
①廃油:揮発油類、灯油類、軽油類
②廃PCB等及びPCB汚染物:トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器
③廃石綿等:飛散型アスベスト廃棄物
特別管理産業廃棄物の取扱い

特別管理産業廃棄物とは爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをいい、建設廃棄物のなかでは廃石綿等、廃油等が該当し、これらは特に厳しい処分基準が定められています。他の廃棄物と混合しないように保管、排出し、処分には十分注意をしてください。
~廃石綿等~
①吹付け石綿を除去したもの
②次のような石綿を含む保温材、耐火被覆材等を除去したもの
・石綿保温材
・けいそう土保温材
・パーライト保温材
・人の接触、気流及び振動等により上記のものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材(比重0.5以下の石綿含有保温材)
③上記のものを除去する際に用いられた養生シート、防じんマスク等の廃棄されたもので石綿の付着しているおそれのあるもの
~廃油~
①揮発油類、灯油類、軽油類(シンナー、燃料等の残り)
②上記のものを使用することに伴って排出される廃油で、引火点70℃未満のもの
③廃酸(ph2以下のもの)
④廃アルカリ(ph12.5以上のもの)
保管基準について

排出事業者は廃棄物が運搬されるまでの間、定められた基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないように廃棄物を保管しなければなりません。具体的には以下のとおりです。
■周囲に囲いが設けられていること
■見やすい箇所に以下の内容の掲示板が設けられていること
・縦横それぞれ60cm以上の掲示板であること
・「産業廃棄物の保管場所である旨」、「廃棄物の種類」、「保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先」、「最大保管高さ」など所定事項
保管の場所から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように、汚水発生のおそれがあれば排水溝等の整備など、必要な措置を講ずることが求められます。保管ばしょには「ねずみ」、「蚊」、「はえ」その他の外注が発生しないようにします。
※石綿を含む産業廃棄物の場合は、「その他の物と混合しないよう、仕切りを設ける等必要な措置」を講ずること、「覆いを設ける、梱包する等により飛散を防止するための必要な措置」を講しなければなりません。
※水銀使用製品の場合は、「その他の物と混合しないよう、仕切りを設ける等必要な措置」を講じなければなりません。
※特別管理産業廃棄物を保管する場合にはその種類などの表示や他の物と混合しないよう仕切りなどの措置、種類別に揮発防止や腐食防止、高温防止などの措置も義務付けられています。
処理を委託する場合

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、委託基準に従い都道府県等の許可を受けた業者に処理を委託することになります。委託をする場合、「業者が収集運搬(または処分)の許可を保有している」こと、「委託する産業廃棄物がその許可の品目の中に含まれている」ことを確認しましょう。確認は委託する業者の「産業廃棄物処理業許可証」で確認ができます。委託契約を結ぶ場合は、法律で定められた内容の契約書を作成してください。
~委託契約書~
廃棄物の種類や量、運搬や処理の方法などを明らかにし、各業者と書面で委託契約を締結しなければなりません。(委託契約書は排出事業者が作成します。)
委託契約を締結する際は、大きく3つのパターンに分けられます。
「①収集運搬のみを委託する場合」、「②処分のみを委託する場合」、「③収集運搬と処分をひとつの業者に委託する場合」それぞれ必要な記載事項を確認していきましょう。
委託契約書に記載すべき内容

~①収集運搬のみを委託する場合~
■運搬の最終目的地の所在地
(積替保管する際は、別途記載事項があります)
■委託する産業廃棄物の種類
■委託する産業廃棄物の数量
■委託契約の有効期間
■委託者が受託者に支払う料金
■受託者が許可を受けた事業範囲
■産業廃棄物の性状および荷姿
■通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に係わる事項
■他の廃棄物の混合等により生ずる支障に係わる事項
■日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に係わる事項
■委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
■水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
■その他、取り扱いに係わる注意事項
■委託契約の有効期間中に産業廃棄物の情報に変更が生じた際の伝達方法
■委託業務終了時の委託者への報告に係わる事項
■契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱いに係わる事項
~②処分のみを委託する場合~
■処分又は再生場所の所在地
■処分又は再生方法
■施設の処理能力
■最終処分場所の所在地
■最終処分方法
■最終施設の処理能力
■委託する産業廃棄物の種類
■委託する産業廃棄物の数量
■委託契約の有効期間
■委託者が受託者に支払う料金
■受託者が許可を受けた事業範囲
■産業廃棄物の性状および荷姿
■通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に係わる事項
■他の廃棄物の混合等により生ずる支障に係わる事項
■日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に係わる事項
■委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
■水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
■その他、取り扱いに係わる注意事項
■委託契約の有効期間中に産業廃棄物の情報に変更が生じた際の伝達方法
■委託業務終了時の委託者への報告に係わる事項
■契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱いに係わる事項
~③収集運搬と処分をひとつの業者に委託する場合~
■処分又は再生場所の所在地
■処分又は再生方法
■施設の処理能力
■最終処分場所の所在地
■最終処分方法
■最終施設の処理能力
■運搬の最終目的地の所在地
(積替保管する際は、別途記載事項があります)
■委託する産業廃棄物の種類
■委託する産業廃棄物の数量
■委託契約の有効期間
■委託者が受託者に支払う料金
■受託者が許可を受けた事業範囲
■産業廃棄物の性状および荷姿
■通常の保管状況下での腐敗、揮発等性状の変化に係わる事項
■他の廃棄物の混合等により生ずる支障に係わる事項
■日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示に係わる事項
■委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
■水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
■その他、取り扱いに係わる注意事項
■委託契約の有効期間中に産業廃棄物の情報に変更が生じた際の伝達方法
■委託業務終了時の委託者への報告に係わる事項
■契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱いに係わる事項
マニフェストについて

排出事業者が廃棄物処理を委託する場合、マニフェストで管理することが廃棄物処理法により義務付けられています。マニフェスト制度は、排出事業者が処理を委託した産業廃棄物の移動、処理の状況を自ら把握するためにあります。制度導入以前は廃棄物の不適切な処理や不法投棄が続いたことから1990年に導入されました。
~紙マニフェスト~
マニフェストは、7枚綴りの複写式の伝票になっており、排出事業者は「廃棄物の種類」、「数量」、「収集運搬事業者名」、「処分事業者名」などを記入し、廃棄物とともに業者に渡します。各工程で廃棄物の収集運搬や処分が終わると排出事業者のもとにマニフェストが戻ってくる仕組みとなっており、最終的に排出事業者の手元には4枚残ります。伝票は受け取った日から5年間保管します。
~電子マニフェスト~
電子マニフェストは紙マニフェストに記載する情報を電子化したものです。各業者はインターネット上でやりとりをするため、廃棄物の状況をリアルタイムで確認することができます。
伝票の保存や報告書提出が不要であり、紙マニフェストよりも運用が容易です。しかし、「排出事業者」、「収集運搬業者」、「中間処分業者」、「最終処分業者」などすべての事業者が電子システムを導入していなければ活用できません。(導入費用がかかります。)「産廃の引き渡し日」、「運搬終了日」、「処分終了日」からそれぞれ3日以内に情報処理センターに報告をします。
経営的基礎とは

また許可の審査には申請者の「経理的基礎」という基準があります。これは簡単に申しますと、決算書の内容が悪いと許可を出しませんよ、という審査です。
許可を出す行政庁によって基準は様々ですが、例えば愛知県を例にとると次のようになっています。法人が新規で収集運搬許可を取ろうとする場合、自己資本額がマイナス、直前決算の経常利益がマイナス、直前3年間の経常利益の平均がマイナスの場合には許可を取ることができません。申請するときになって慌てないよう、あらかじめ自社の決算書を確認しておきましょう。
お問い合わせ
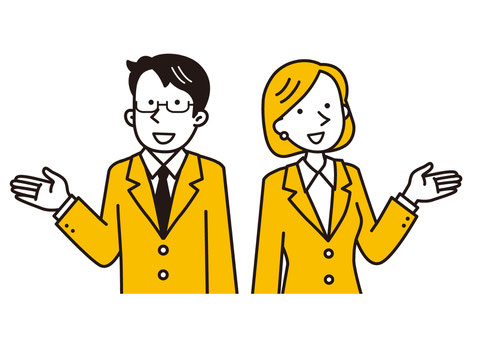
みそらでは建設業許可や経審はもちろん、工事前に行う「農地の一時転用」「道路使用許可」「道路占用許可」「入札参加資格申請」「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。