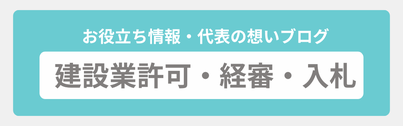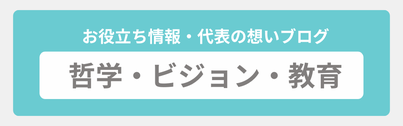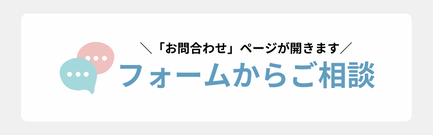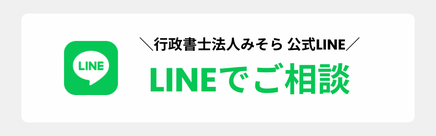残土処分の法規制あれこれ
お客様から「残土の処分に困る」というお悩みを伺います。
2018年度の調査では全国の現場で発生した土砂の20%(約6,000万㎥)が有効利用されていません(日経コンストラクション11月号参照)。熱海の土砂災害を契機に、静岡県は盛土条例、そして来春には全国で盛土規制法(旧宅造規制法)の本格施行による規制が始まり、今後さらに残土の扱いが困難になる方向です。
残土にコンガラ等の産廃が混在していなければ、法律上は「土砂」として扱われます。そのため行政側も残土には廃棄物処理法による強力な規制をかけられません。届出制度を設けているのみで比較的、監視の目が緩い場所として関東圏の悪質業者に狙われたというのが熱海の災害の背景です。静岡県は既に判明している「不適切な盛土」をホームページで公表していますが、その多くが富士山周辺のエリアに偏って存在していることからもそれを伺わせます。
建設現場から発生する産廃は、そのまま原材料として売却される金属類のほか、中間処分場で破砕等された後、再生材料とされるものと最終処分場で埋め立てられるものに分かれて処理されます。この一連の流れはマニフェストで管理され違反者には厳しい罰則があります。
新しい盛土規制法の運用が本格的に始まると、宅地等を造成する場合には土砂の出所に関係なく市街地や宅地を含め法令で規制がかかります。また発生後、工事現場に向かわない残土については、元請会社にストックヤードや最終処分場へ搬入したことを証明する書面交付を受ける義務を課し、残土処分の責任を持たせる制度を作りました。産廃のマニュフェストの仕組みを簡単にしたようなものです。
来年度以降は造成に着手する前の許認可が必要な案件が増えるだけでなく、役所も不慣れな審査が急増して手続きに時間を要する見込みです。工期の検討にあたっては出来るだけ余裕をみていただければと思います。

静岡県は新しい盛土環境条例として再スタート
新しい盛土規制法の本格的な運用開始に合わせて、静岡県は盛土条例を改正し、
盛土環境条例として再スタートします。
改正のポイントは下記のとおりです。
1.名称を「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例」に改める。
2.盛土規制法に委ねる災害の防止に関連する規定は削る。
3.「基準不適合土石による盛土、埋立て等の禁止」、「土石の搬入前の汚染のおそれの確認・県への報告」、「水質や土壌の調査の実施」などの盛土条例の生活環境の保全に関する枠組みを維持する。
4.届出の対象は、①盛土規制法の許可が必要な盛土・堆積、②埋立てとする。
5.盛土条例と同様に、届出の対象とする規模は1,000㎡以上とする。
6.工事に伴う一時堆積、土石の現地流用による盛土等は、届出や水質・土壌の分析調査の 対象外とする。
7.埋立てについては、周辺住民に対し、説明会の開催その他の周知の実施を求める。
8.水質・土壌の分析調査を不要とする要件(土石の搬入前に汚染のおそれのないことを確認 できた「開発型盛土」など)を規則に定める。