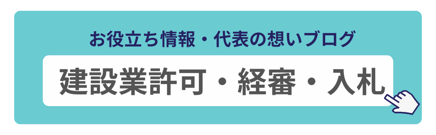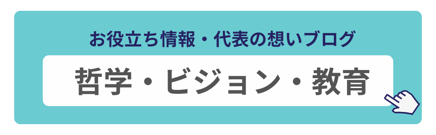建設業界で人手不足が叫ばれて久しいですが、経営状況の良いお客様であっても、若手、ベテランを問わず、人員の確保には困っていらっしゃる声をよく伺います。
とはいえ外国人の雇用や定着は一部のお客様からは上手くいっているというお話を伺っていましたが、採用や育成の難しさ等の理由でなかなか主流にはなりにくなと感じていたところでした。
しかしここにきて「いよいよ外国人の雇用に挑戦してみるしかない」というお話を続けざまに伺いましたので、ここで改めて建設業界で働く外国人の在留資格について振り返ってみることにしました。
行政書士としては、外国人の雇用を検討する際に最も注意をしていただきたいのは「在留資格と在留期間」のふたつです。
採用を検討しているお客様には「まず在留カードと履歴書を見せてください」とお伝えしています。
初めてという方にはピンとこないと思いますが、外国籍の方が日本に滞在するためにはそれぞれ日本政府から与えられた在留資格が必要であり、ひとりひとり在留資格には有効期間があります。
在留資格にふさわしい活動内容が終わったり、期間が満了した場合には、日本から出国をしてください、というのが日本政府の基本的なスタンスです。
例えば、旅行で日本を訪れる方は「短期滞在」という在留資格で日本に入国し計画した旅行が終われば出国をしなければなりません。留学生の方も同じです。在留資格は「留学」であり、留学先の学校を卒業や中退したら出国をしなければなりません。社会人の在留資格は二十数種類ありますが、基本的な考え方は同じです。特に社会人の場合には、一部の在留資格を除いて個々に働いてよい業界や職種が限定されています。
このルールを守らずに就労をすると、本人の不法な就労はもちろん、雇用した事業者も不法な就労を助長した責任を問われることになります。この特徴を良く理解していただくことが、初めて採用を検討する際に大切なことです。
また建設業の場合には、現場で作業をする在留資格、監理・設計・営業・事務をする在留資格、のふたつが明確に区分をされています。とても間に合う人だからといって、色々な仕事を任せてしまうと、こちらもやはり不法な就労となってしまうリスクがあります。
以上の注意点を参考にしていただくため、簡単な表を作成しました。あくまで概略を記しただけですのでその旨をご理解いただき、個別の具体的な案件については、必ず入管当局や行政書士等の専門家にお尋ねください。