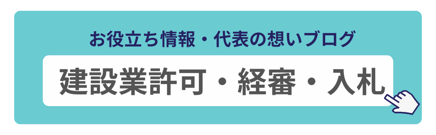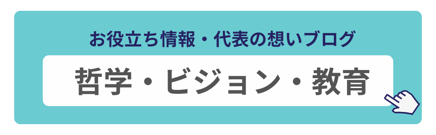建設業のコンプライアンス
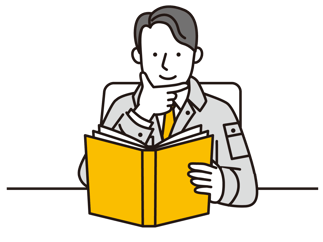
目次
建設業を営むにあたっては、コンプライアンスを重視し、さまざまな法令やルールを遵守することが求められます。ここでは、行政書士の視点から特に注意すべき項目についてご説明いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
許可の欠格要件について(建設業法第8条、同法第17条(準用))
なお、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
◆許可申請書や添付書類に虚偽の記載がある場合
◆重要な事実に関する記載が欠けている場合
◆許可申請者・その役員等・令第3条に規定する使用人が、欠格要件のいずれかに該当する場合
①破産手続きが始まり、まだ権利を回復していない人
②過去に建設業の許可を取り消されてから、5年が経っていない人
③許可取り消し通知を受けた後、その処分が決まるまでの間に廃業などを届け出て、その届出から5年が経っていない人
④前号の期間内に廃業届などが出された際、その通知の60日以内に当該法人の役員などであった人、または個人の政令で定める使用人であった人で、その届出から5年が経っていない人
⑤営業停止命令の期間がまだ終わっていない人
⑥許可を受けようとする建設業について、営業を禁止されている期間がまだ終わっていない人
⑦禁錮以上の刑を受け、刑期を終えるか、刑の執行を受けなくなってから5年が経っていない人
⑧建設業関連の法律や刑法、暴力団排除法などに違反して罰金刑を受け、刑期を終えるか、刑の執行を受けなくなってから5年が経っていない人
⑨暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年が経っていない人
⑩心身の病気などで、適切に建設業を営むことができないと国土交通省令で定められた人
⑪未成年者で、事業について成人と同じ能力を持たない場合、その法定代理人(保護者など)が上記のいずれかの条件に該当する人
⑫法人の役員などや、政令で定める使用人のうち、上記のいずれかの条件に該当する人がいる法人
(ただし、その人が許可取り消しや営業禁止などを受ける前から、当該法人の役員などで、その責任が限定的な場合は除きます)
⑬個人の政令で定める使用人のうち、上記のいずれかの条件に該当する人がいる個人事業主
(ただし、その人が許可取り消しや営業禁止などを受ける前から、当該個人の政令で定める使用人であった場合で、その責任が限定的な場合は除きます)
⑭暴力団関係者がその事業活動を実質的に支配している場合
監督処分について(最終改正:令和5年3月3日国不建第578号)
監督処分とは、法令違反があった場合に行政機関が発する命令の総称です。主な種類は以下の通りです。
指示処分
建設業者が違反や不適正な事実を是正するために 具体的にとるべき措置 を行政庁が命じます。
営業停止処分
建設業者に対して 1年以内の期間で、営業の全部または一部を停止 するよう命じます。(原則、故意または重大な過失による不正行為の場合に適用されます。)
許可取消処分
建設業者が 許可要件を満たさなくなった場合、欠格要件に該当した場合、重大な不正行為を行った場合 に実施されます。
監督処分の具体的な基準について
監督処分は建設業の許可行政庁(地方整備局、都道府県)ごとに基準を定めて運用をしています。ここでは国土交通省の監督処分の基準を例に挙げて解説をします。
(最終改正 令和5年3月3日国不建第578号)
公衆危害に関する監督処分の基準
建設業者が工事を適切に施工せず、公衆に危害を与えた場合の処分は、危害の程度や状況に応じて以下のように決まります。
重大な危害を及ぼした場合
・公衆に死亡者または負傷者3人以上が発生
・役職員が業務上過失致死傷罪などで刑に処せられた場合
⇒ 営業停止処分(7日以上)
軽微な危害の場合
⇒ 指示処分
重大な危害を及ぼすおそれが大きい場合
・危害が発生する前でも、公衆に重大な危害を及ぼすおそれがあると認められるとき
⇒ 直ちに危害防止措置の勧告
→ 必要に応じて指示処分
→ 指示に従わない場合は営業停止処分(7日以上)
資材に起因する危害の場合
・違反行為が建設資材に原因があると認められるとき
⇒ 必要に応じて指示処分
建設業者の業務に関する談合・贈賄等(刑法違反・独禁法違反など)
建設業者が談合や贈賄などの不正行為を行った場合、関与者や内容によって監督処分が変わります。
①代表権のある役員等が刑に処せられた場合
→営業停止処分(1年間)
②代表権のない役員等や政令で定める使用人が刑に処せられた場合
→営業停止処分(120日以上)
③上記①・②以外の場合
→営業停止処分(60日以上)
④独占禁止法に基づく排除措置命令・課徴金納付命令が確定した場合(通知を含む)
→営業停止処分(30日以上)
⑤独禁法第3条違反で①~④により営業停止を受け、その後10年以内に再度①~④に該当する事由があった場合
→本来の営業停止期間を2倍に加重(ただし最長1年)
請負契約に関する不誠実な行為と監督処分
虚偽申請①
入札前の調査資料や競争参加資格確認申請書などに虚偽記載、不正行為を行った場合(ただし②に該当する場合を除く)
→営業停止処分(15日以上)
虚偽申請②
完成工事高を水増しするなど虚偽申請を行い、その結果を経審で利用し、公共発注者が資格審査に用いた場合
→営業停止処分(30日以上)
上記②に加え、国交省告示85号に基づく監査の対象資料(財務諸表等)に虚偽があった場合
→営業停止処分(45日以上)
主任技術者等の不設置
主任技術者・監理技術者を置かなかった、または資格を満たさない者を置いた場合
→営業停止処分(15日以上)
虚偽の実務経験証明により不正取得した資格者を主任技術者・監理技術者として配置していた場合
→営業停止処分(30日以上)
主任技術者・監理技術者の専任義務違反
→指示処分(従わなければ営業停止処分 7日以上)
粗雑工事等
手抜きや粗雑施工により工事目的物に重大な瑕疵が発生した場合
→営業停止処分(15日以上)
上記が低入札価格調査対象工事である場合
→営業停止処分(30日以上)
施工体制台帳等の不作成
施工体制台帳・施工体系図を作成しない、または虚偽のものを作成した場合
→営業停止
建設工事の施工等に関する他法令違反

建設工事に関して、他の法律や規則に違反した場合も監督処分の対象となることがあります。処分の判断では、違反の内容や程度、建設業の営業との関連などを総合的に考慮し、「建設業者として適切かどうか」が評価されます。法人の場合は、役員や政令で定められた使用人、または法人自体に違反があった場合に、監督処分が行われます。
労働安全衛生法違反(工事関係者の事故等)
◆役員や従業員が労働安全衛生法違反で刑に処せられた場合:指示処分
◆工事関係者に死亡者や3人以上の負傷者が出た場合:営業停止処分(3日以上)
建設工事の施工等に関する法令違反
① 建築基準法違反
◆役員等が懲役刑に処せられた場合:営業停止処分(7日以上)
◆それ以外の役職員が刑に処せられた場合:営業停止処分(3日以上)
◆建築基準法に基づく命令に違反した場合:指示処分(必要に応じて3日以上の営業停止)
◆違反が建設資材に起因する場合:指示処分(必要に応じ)
② 労働基準法違反
◆役員等が懲役刑:営業停止処分(7日以上)
◆それ以外の役職員が刑に処せられた場合:営業停止処分(3日以上)
③ 宅地造成・廃棄物処理法違反
◆役員等が懲役刑:営業停止処分(15日以上)
◆それ以外の役職員が刑に処せられた場合:営業停止処分(7日以上)
④ 特定商取引法違反
◆役員等が懲役刑:営業停止処分(7日以上)
◆それ以外の役職員が刑に処せられた場合:営業停止処分(3日以上)
◆指示処分や業務停止命令を受けた場合:指示処分(必要に応じ3日以上の営業停止)
⑤ 賃貸住宅管理業法違反
◆役員等が懲役刑:営業停止処分(7日以上)
◆それ以外の役職員が刑に処せられた場合:営業停止処分(3日以上)
◆指示処分や特定賃貸借契約の締結停止命令を受けた場合:指示処分(必要に応じ3日以上の営業停止)
信用失墜行為等
① 税法違反(法人税法・消費税法等)
◆役員等や政令で定める使用人が懲役刑の場合:営業停止処分(7日以上)
◆それ以外の役職員が刑に処せられた場合:営業停止処分(3日以上)
② 暴力団排除法違反
◆役員等や政令で定める使用人が刑に処せられた場合:営業停止処分(7日以上)
健康保険・厚生年金・雇用保険法違反
① 役員等が懲役刑の場合
◆営業停止処分(7日以上)
◆それ以外の役職員が刑に処せられた場合:営業停止処分(3日以上)
② 健康保険、厚生年金保険、雇用保険未加入や立入検査拒否等
◆保険担当部局による通知で違反が確認された場合:指示処分
◆指示に従わない場合:営業停止処分(3日以上)
一括下請負等
◆建設業法第22条違反:営業停止処分(15日以上)
(元請負人に誠実性が欠ける場合等は減軽される場合があります)
◆建設業法第26条の3第9項違反:営業停止処分(15日以上)
主任技術者等の変更
◆工事管理が著しく不適当で公益上必要な場合:書面で変更勧告
◆指示処分に従わない場合:営業停止処分(7日以上)
無許可業者等との下請契約
◆許可を受けない業者と契約した場合:営業停止処分(7日以上)
(酌量すべき情状がある場合は、減軽される場合があります)
◆下請代金が政令で定める金額以上の契約:営業停止処分(7日以上)
(酌量すべき情状がある場合は、減軽される場合があります)
◆営業停止処分を受けた者と知って契約した場合:営業停止処分(7日以上)
履行確保法違反
◆第5条違反:指示処分
→従わない場合:営業停止処分(15日以上)
◆第3条第1項・第7条第1項違反:指示処分
→従わない場合:営業停止処分(7日以上)
建設業を営む者に対する罰則について
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法第47条)
◆無許可営業
建設業の許可を受けずに建設業を営んだ者
(軽微な工事のみは除く)【法第3条第1項】
◆下請契約違反
下請契約の締結制限に違反して契約した者【法第16条】
◆営業停止・禁止違反
処分に違反して建設業を営んだ者【法第29条の4第1項】
◆虚偽の許可申請
虚偽や不正な事実に基づき建設業の許可(更新含む)を受けた者【法第3条】
6月以下の懲役または100万円以下の罰金(法第50条)
◆虚偽の申請書提出
許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合【法第5条・第6条第1項・第17条】
◆届出の不提出・虚偽
変更届(決算変更届含む)を提出せず、または虚偽の記載で提出した場合【法第11条第1~4項】
◆基準不適合・欠格要件届出の未提出
2週間以内に届出をしなかった場合【法第11条第5項】
◆経営状況分析・経営規模等評価の虚偽申請
虚偽の記載で申請した場合【法第27条の24第2~3項・第27条の26第2~3項】
100万円以下の罰金(法第52条)
◆主任技術者・監理技術者未設置【法第26条第1~3項】
◆許可のない業者に許可が必要な工事を施工させた場合【法第26条の2】
◆許可失効後の通知未提出【法第29条の3第1項】
◆報告・資料提出の義務違反
◇登録経営状況分析機関や行政の要求に報告・提出せず、虚偽の報告・提出を行った場合【法第27条の24第4項・第27条の26第4項】
◇国土交通大臣等への報告・検査拒否や妨害【法第31条第1項・法第42条の2第1項】
10万円以下の過料(法第55条)
◆廃業届出の怠り【法第12条】
◆審査会出頭要求への不応答【法第25条の13第3項】
◆標識未掲示
店舗や建設現場で公衆の見やすい場所に標識を掲げなかった場合【法第40条】
◆許可を受けていないのに受けたと誤認される表示【法第40条の2】
◆帳簿・図書の不備
営業所ごとに必要な帳簿を備えず、記載や保存を怠った場合【法第40条の3】
工事請負契約書について
工事請負契約とは、工事の受注者(施工業者)と発注者(依頼者)が結ぶ契約のことです。建設業法では、契約は書面で作成することが義務とされています。
※見積書だけ、またはFAXやメールでの受発注は、契約書を作成したことにはなりません。
契約内容を事前に書面で明確にすることで、請負代金や施工範囲に関するトラブルを未然に防ぐことが目的です。契約書には以下の項目を必ず記載する必要があります。
工事請負契約書に記載すべき内容
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期および完成の時期
④工事を施工しない日や時間帯の定め(ある場合)
⑤前金払いや出来形部分の支払の時期および方法(ある場合)
⑥設計変更や工事中止などに伴う工期・代金・損害の負担や算定方法
⑦天災など不可抗力による工期・損害の取り扱い
⑧物価変動等に伴う請負代金や工事内容の変更
⑨施工による第三者への損害に関する賠償金の負担
⑩注文者が資材や機械を提供・貸与する場合の内容・方法
⑪工事完成確認の検査時期・方法および引渡し時期
⑫工事完成後の請負代金の支払時期および方法
⑬工事目的物の種類・品質が契約に適合しない場合の責任や保証措置
⑭履行遅延や債務不履行時の遅延利息・違約金など
⑮契約に関する紛争の解決方法
⑯その他、国土交通省令で定める事項
書面での契約締結方法
公共工事・民間工事いずれの場合も、契約内容は書面で作成することが必要です。
契約書の形式は、以下のいずれかで締結します。
◆請負契約書
◆注文書・請書 + 基本契約書
◆注文書・請書 + 基本契約約款
印紙代について
工事請負契約書には印紙税が必要です。印紙代は契約金額に応じて決まっており、国税庁のホームページに掲載されている最新の印紙税額一覧表で確認するのが確実です。国税庁印紙税一覧表
※令和6年4月1日以降適用分、令和9年3月31日までは軽減税率が適用されています
◆1万円超200万円以下 :200円
◆200万円超300万円以下 :500円
◆300万円超500万円以下 :1,000円
◆500万円超1,000万円以下 :5,000円
◆1,000万円超5,000万円以下 :10,000円
◆5,000万円超1億円以下 :30,000円
◆1億円超5億円以下 :60,000円
(以下、省略)
契約書を作成する際は、作成する通数ごとに印紙代が必要です。印紙に押す消印については、当事者双方が行う必要はなく、契約のどちらか一方が行えば十分です。消印は印鑑でなくても、ペンで印を付けるだけでもかまいません。また、工事注文書と請書を用いる場合には、請書のみに印紙を貼り、金額は規定の表に基づいて計算してください。
特定許可業者の義務
施工体制台帳について
特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事の下請契約の請負代金が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合、施工体制台帳を作成する義務があります。施工体制台帳を作成し元請業者が現場の施工体制を把握することで、品質・工程・安全上のトラブル、違法な一括下請負、安易な重層下請の発生を防止することが目的です。台帳には、工事を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、工期、各業者の技術者の氏名などを記載します。下請契約は建築工事の請負契約を指し、資材納入、調査、運搬、警備業務等は対象外です。
施工体制台帳の作成が必要なケース
◆元請業者が一次下請に3,000万円、一次下請に2,600万円、運搬業者に200万円の契約をした場合
→ 下請契約の総額は5,600万円で施工体制台帳の作成が必要です。建設工事に該当しない業務は含まれません。
施工体制台帳の作成が不要なケース
◆元請業者が一次下請に2,000万円、一次下請に2,000万円、運搬業者に200万円の契約をした場合
→ 下請契約の総額は4,000万円で作成は不要です。建設工事に該当しない業務は含まれません。
施工体制台帳の備置・保存・提出・閲覧
◆公共工事・民間工事問わず作成が必要
◆工事現場ごとに、請け負った工事の目的物を発注者に引き渡すまで備え置く
◆工事完了後は5年間保存
◆公共工事では入札契約適正化法に基づき発注者に写しを提出
◆民間工事では発注者から請求があれば閲覧に供する
施工体系図について
◆施工体系図は施工体制台帳に基づき作成し、下請負人の施工分担関係を一目で把握できる図
◆施工体制台帳の作成対象工事では施工体系図の作成も義務
◆工事期間中は民間工事は「見やすい場所」、公共工事は「工事関係者および公衆が見やすい場所」に掲示
◆下請業者の変更があった場合は速やかに表示を更新
元請 特定建設業者の責務
◆現場での法令遵守指導の実施
◆下請業者の法令違反については是正指導
◆下請業者が是正しないときの許可行政庁への通報
指導すべき主な法令
特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負い元請となった場合、下請業者が関連する諸法令に違反しないよう指導する責務があります。対象となる下請業者は、直接契約した下請業者だけでなく、工事に携わる全ての下請業者です。指導すべき主な法令と留意事項は次のとおりです。
建設業法
下請負人の保護、技術者の設置など、建設業法全体が対象
特に以下の項目に留意
◆建設業の許可(第3条)
◆一括下請負の禁止(第22条)
◆下請代金の支払(第24条の3、第24条の6)
◆検査および確認(第24条の4)
◆主任技術者および監理技術者の設置(第26条、第26条の2)
建築基準法
◆違反建築の施工停止命令等(第9条第1項、第10項)
◆危害防止の技術基準(第90条)
宅地造成等規制法
◆設計者の資格等(第9条)
◆宅地造成工事の防災措置(第14条第2項~第4項)
労働基準法
◆強制労働の禁止(第5条)
◆中間搾取の排除(第6条)
◆賃金の支払方法(第24条)
◆労働者の最低年齢(第56条)
◆年少者・女性の坑内労働の禁止(第63条、第64条第2項)
◆安全衛生措置命令(第96条の2第2項、第96条の3第1項)
職業安定法
◆労働者供給事業の禁止(第44条)
◆暴行等による職業紹介の禁止(第63条第1号、第65条第8号)
労働安全衛生法
◆危険・健康障害の防止(第98条第1項)
労働者派遣法
◆建設労働者の派遣の禁止(第4条第1項)
著しく短い工期の禁止について
建設業において就業者の長時間労働を是正するためには、まず工事の工期を適正に設定することが不可欠です。建設工事の注文者は、その工事の施工に通常必要とされる期間に比べて著しく短い工期を設定して請負契約を結ぶことは禁止されています。
短い工期は長時間労働の原因となりやすく、特に令和6年4月からは建設業にも「時間外労働時間の上限規制」が適用されているため、この規制を超える時間外労働は労働基準法違反となります。
なお、災害時の復旧・復興事業はこの規制の適用外とされています(令和6年4月1日~)。また、上限規制を超える違法な時間外労働を前提として工期を設定した場合には、元請と下請の双方が合意していたとしても「著しく短い工期」とみなされることになります(令和6年4月1日~)。
著しく短い工期の判断材料について
工期が「著しく短い」と判断されるかどうかは、さまざまな状況や資料をもとに総合的に判断されます。具体的には、次のような点が考慮されます。
◆見積依頼の段階で元請負人が下請負人に提示した条件
◆締結された請負契約の内容
◆下請負人が「著しく短い工期」と認識していたかどうか
◆過去に行われた同種または類似工事の実績
◆下請負人が元請負人に提出した見積内容
◆当該工期を前提として契約を締結した経緯や事情
◆元請負人が工期についてどのように考えていたか
◆賃金台帳など、労働時間や働き方を確認できる資料
これらを基に、実際の工期が適正であったか、それとも不当に短かったかを判断されることになります。
著しく短い工期の判断の視点について
まず一つ目の視点は、契約で定められた工期が「工期基準」で示された内容を踏まえておらず、その結果、下請負人が違法な長時間労働など不適正な状態で工事を行わざるを得ない状況になっていないかという点です。
次に、過去の同種類似工事の工期と比較した場合に今回の工期が短く設定されており、そのために下請負人が不適正な労働環境で工事を進めざるを得ない状況となっていないかが確認されます。
さらに、下請負人が見積書で示した工期と比べて契約で定められた工期が短く、そのことによって不適正な労働を強いられる恐れがないかという点も重要な判断材料となります。
工期変更時にも適用される点について
「著しく短い工期」の禁止は、当初契約の締結時だけでなく、その後に工事が当初の計画どおり進まなかった場合や工事内容の変更が生じた場合にも適用されます。すなわち、変更契約を結んで工期を見直す際にも、適正な工期を確保することが求められます。
禁止に違反した場合の措置について
国土交通大臣などの行政庁は、著しく短い工期で契約を締結した発注者に対して勧告を行うことができます。さらに、勧告に従わない場合には、その事実が公表されることになります。また、建設工事の注文者が建設業者である場合には、勧告だけでなく、指示処分が行われることもあります。
下請け代金の適正な支払いについて
下請代金の支払いが適正に行われないと、下請負人の経営が不安定になるだけでなく、結果として手抜き工事や労災事故を招き、建設工事の適正な施工を確保することが難しくなるおそれがあります。そのため、建設業法では工事の適正な施工と下請負人の利益を守る目的で、下請代金に関する規定を設けています。
①元請負人は、注文者から出来形部分の支払いまたは工事完成後の支払いを受けたとき、その対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する代金を1か月以内、かつ、できる限り短い期間で支払わなければなりません。
②下請代金のうち労務費に当たる部分は現金で支払うよう配慮が必要です。手形で支払う場合でも、手形期間は120日以内で、できるだけ短く設定しなければなりません。
③元請負人が前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対しても資材購入や労働者募集など工事着手に必要な費用を前払金として支払うよう努める必要があります。建設工事の準備行為は下請負人が行う場合も多いためです。
④下請工事の完成を確認する検査は、下請負人から完成の通知を受けてから20日以内に行う必要があります。また、検査後に下請負人から引渡しの申出があった場合は、直ちに引き渡しを受けなければなりません。通知や申出は口頭でも可能ですが、紛争防止のため書面で行うのが望ましいです。
⑤特定建設業者は、下請負人(特定建設業者や資本金4,000万円以上の法人を除く)から引渡しの申出を受けた日から50日以内に下請代金を支払わなければなりません。
また、赤伝処理を行う場合は元請・下請双方の協議・合意が必要です。さらに、安全衛生費や建設廃棄物処理費用を下請代金から差し引く場合は、その内容を見積条件や契約書に明示しておく必要があります。
なお、特定建設業者は「出来形払いや完成払いを受けた日から1か月以内」と「引渡し申出日から50日以内」という二つの義務を負います。したがって、支払期日の定めがない場合には、引渡し申出日から50日以内、または出来形払いや完成払いを受けた日から1か月以内のいずれか早い期日で支払う必要があります。
書類の保存義務について
帳簿の作成と保存について
建設業者は、営業所ごとに国土交通省令で定められた内容を記載した帳簿を備え、帳簿と営業に関する図書を保存する義務があります。帳簿の保存期間は原則5年間ですが、発注者(宅地建物取引業者を除く)と締結した住宅の新築工事に関する帳簿については10年間の保存が必要です。
帳簿に記載する内容
① 営業所の代表者の氏名と就任日
② 請負契約に関する事項(工事の名称・現場所在地、契約日、注文者の商号・住所・許可番号、完成検査完了日、引渡し日)
③ 下請契約に関する事項(下請工事の名称・所在地、契約日、下請負人の商号・住所・許可番号、完成検査完了日、引渡し日)
帳簿に添付すべき書類
① 請負契約書またはその写し
② 特定建設業者が一般建設業者(資本金4,000万円以上の法人を除く)に下請負した場合の支払証明書類(領収書など)またはその写し
③ 施工体制台帳(元請工事に限る)の必要部分(主任技術者・監理技術者等の情報、下請業者の商号・許可番号、工事内容・工期など)
※添付書類はスキャナで読み取り、営業所で表示する方法でも保存可能です。
営業に関する図書の保存について
営業に関する図書の保存期間は10年間で、対象は元請業者に限られます。保存すべき図書には次のものがあります。
◆工事目的物の完成時の状況を示す完成図(作成または発注者から提供を受けた場合)
◆発注者との打合せ記録(工事内容に関するものを相互に交付した場合)
◆施工体系図(重層下請構造の全体像を明らかにするため、作成義務がある業者が作成したもの)
廃棄物処理の基本知識
建設工事に伴って発生する廃棄物には、発生場所が一定しない、発生量が膨大、種類が多岐にわたり混合状態で排出されることが多いが分別すれば再利用が可能、取扱い業者が多数存在する、といった特徴があります。特に木くずやがれき類など解体に伴う廃棄物は不法投棄が多く、生活環境保全上の重大な問題となっています。
このため、建設廃棄物の適正処理にあたっては、元請業者を中心とした排出事業者がその責任を果たすとともに、発注者、設計者、下請業者、処理業者、製造事業者など関係者がそれぞれの役割を担うことが求められます。
排出事業者の責務
建設工事では、原則として元請業者が排出事業者に該当します。建設工事には「建設工事の発注者」「発注者から直接工事を請け負った元請業者」「元請業者から工事を請け負った下請業者」など、多数の関係者が存在するため、廃棄物処理における責任の所在が不明確になりやすいという特徴があります。
この点を明確にするために、建設廃棄物については、実際の施工を下請業者が行っていたとしても、発注者から直接請け負った元請業者が排出事業者とされ、処理責任を負う仕組みとなっています。
建設廃棄物の減量化について
排出事業者は、建設廃棄物の発生をできる限り抑制し、再生利用を推進することによって減量化を図るとともに、再生資材の活用を積極的に進めなければなりません。
自己処理について
排出事業者は、自らの責任において建設廃棄物を廃棄物処理法に従い、適正に処理しなければなりません。自己処理には排出事業者が直接行う運搬、中間処理(再生を含む)、最終処分が含まれ、それぞれについて廃棄物処理法の基準に従う必要があります。
委託処理について
排出事業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、廃棄物処理法に定める委託基準に従い、「収集運搬業者」、「中間処理業者」、「最終処分業者」とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行い、適正な処理費用の支払い等、排出事業者として適正な処理を確保しなければなりません。また、現場内で行う処理であっても、下請業者に処理させる場合は、委託処理に該当します。
発注者や関係者の責務と役割
建設工事では、廃棄物の処理責任は原則として元請業者にありますが、元請業者だけでなく、発注者や設計者、下請業者、処理業者、メーカーなど多くの関係者が関わっています。
それぞれの立場で「発生をできるだけ減らす」「再利用できるものは活用する」「適切に処理する」ことを意識して取り組む必要があります。
発注者
設計段階から廃棄物を減らす工夫を求めるとともに、処理方法について条件を明示します。
設計者
発注者の意向をふまえ、廃棄物の発生抑制や再利用を考慮した設計を行います。
下請業者
元請業者(排出事業者)に協力し、廃棄物の減量や再利用に努めます。
処理業者
元請業者との契約に基づき、法律に従って廃棄物を適正に処理します。
メーカー(製造事業者)
梱包材の簡素化など廃棄物の発生抑制に努め、製品が廃棄される際に適正処理がしやすいように配慮します。
建設廃棄物の種類
建設廃棄物には、工事そのものから出るものと、現場事務所などから出るものがあります。
排出事業者は、それぞれの廃棄物に応じたルールに従い、適正に処理しなければなりません。
◆現場事務所などから出る廃棄物 → 一般廃棄物として市町村のルールに従って処理
◆工事から出る廃棄物 → 産業廃棄物として法律に従って処理
一般廃棄物
◆生ごみ
◆新聞、雑誌など
産業廃棄物(建設業でよく出るもの)
①廃プラスチック類 … 梱包材、ビニール、ゴムくず、廃タイヤ、シート類
②ゴムくず … 天然ゴムのくず
③金属くず … 鉄筋くず、足場パイプ、金属加工くずなど
④ガラス・陶磁器くず … ガラス破片、タイル、耐火れんがなど
⑤がれき類 … コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片など
⑥汚泥 … 掘削やシールド工法で出る泥水・掘削土など
⑦木くず … 型枠・足場材、内装残材、伐採材、解体材など
⑧紙くず … 段ボール、梱包材、壁紙くずなど
⑨繊維くず … 廃ウエス、縄、ロープなど
⑩廃油 … 防水アスファルトやアスファルト乳剤の残り
①~⑤は「安定型最終処分場」で処理できるもの(ただし一部例外あり)。
特別管理産業廃棄物(注意が必要なもの)
廃油 … 揮発油、灯油、軽油など
PCB廃棄物 … トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器など
廃石綿(アスベスト) … 飛散性の高いアスベスト廃棄物
特別管理産業廃棄物の取扱い
特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性などを持ち、人の健康や生活環境に重大な被害を及ぼすおそれがある廃棄物のことです。
建設廃棄物の中では、廃石綿(アスベスト)や廃油などがこれにあたり、他の廃棄物に比べて 特に厳しい処理基準 が定められています。混合せずに分けて保管・排出し、処分には十分な注意が必要です。
廃石綿等(アスベスト関連廃棄物)
◆吹付け石綿を除去したもの
◆石綿を含む保温材や耐火被覆材(例:石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材)
◆特に飛散の危険が高い軽量保温材(比重0.5以下の石綿含有材)
◆除去作業に使われた養生シートや防じんマスクなど、石綿が付着している可能性のあるもの
廃油
◆揮発油、灯油、軽油など(シンナーや燃料の残りを含む)
◆引火点70℃未満の危険な廃油
◆強い酸性の廃液(pH2以下)
◆強いアルカリ性の廃液(pH12.5以上)
保管基準について
排出事業者は、廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境の保全に支障が生じないように保管 しなければなりません。そのため「産業廃棄物保管基準」に基づき、以下の条件を守る必要があります。
一般的な保管基準
保管場所は 周囲を囲い で仕切ること
保管場所には、見やすい位置に 掲示板(縦横60cm以上) を設置すること
掲示内容
・産業廃棄物の保管場所である旨
・廃棄物の種類
・管理者の氏名または名称・連絡先
・最大保管高さ など
また、廃棄物が 飛散・流出・地下浸透・悪臭の発散 をしないように管理し、汚水発生のおそれがあれば排水溝を整備する必要があります。さらに、「ねずみ」「蚊」「はえ」などの害虫が発生しないように対策を講じます。
特に注意が必要な廃棄物
◆石綿(アスベスト)含有廃棄物
→ 他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける、覆いや梱包で飛散を防止すること
◆水銀使用製品
→ 他の廃棄物と混合しないように仕切りを設けること
◆特別管理産業廃棄物
→ 種類を明示したうえで、他の廃棄物と混合させないこと
→ 揮発防止、腐食防止、高温防止など、種類に応じた追加措置を講じること
処理を委託する場合
排出事業者が産業廃棄物の処理を他者に委託する際には、「委託基準」 に従い、必ず都道府県等の許可を受けた業者に委託しなければなりません。委託にあたっては次の確認が必須です。
◆委託先の業者が 収集運搬業または処分業の許可を有していること
◆委託する産業廃棄物の種類が、その許可証に記載されている品目に含まれていること
これらは、業者が保有する 「産業廃棄物処理業許可証」 により確認できます。
委託契約書の作成
委託契約を結ぶ際には、法律で定められた内容 を盛り込み、廃棄物の種類・量・運搬方法・処理方法を明確にした契約書を作成し、書面で締結しなければなりません。(契約書の作成は排出事業者の責任で行います。)
契約パターンと必要事項
委託契約は大きく分けて3つのパターンがあります。
◆収集運搬のみを委託する場合
◆処分のみを委託する場合
◆収集運搬と処分を一括して委託する場合
それぞれの場合に応じて、契約書に記載すべき事項が異なるため、必ず確認のうえで契約を締結する必要があります。
委託契約書に記載すべき内容
委託契約書には、法律で定められた記載事項を明確に記載する必要があります。大きく「共通して必要となる事項」と「委託の形態によって異なる事項」に分けられます。
共通事項
収集運搬・処分のいずれを委託する場合も、次の内容を契約書に明記する必要があります。
◆委託する産業廃棄物の種類と数量
◆委託契約の有効期間
◆委託者が受託者に支払う料金
◆受託者が許可を受けた事業範囲
◆産業廃棄物の性状および荷姿
◆保管中における腐敗や揮発など性状の変化に関する事項
◆他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
◆JIS C0950号に基づく含有マークの表示に関する事項
◆石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
◆水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
◆その他の取り扱いに関する注意事項
◆契約期間中に情報変更が生じた際の伝達方法
◆委託業務終了時の報告に関する事項
◆契約解除時における未処理産業廃棄物の取り扱いに関する事項
個別事項
委託の形態ごとに、上記の共通事項に加えて以下の内容が必要となります。
①収集運搬のみを委託する場合
◆運搬の最終目的地の所在地(積替保管を行う場合は、別途その旨を記載)
②処分のみを委託する場合
◆処分または再生場所の所在地
◆処分または再生方法
◆処理施設の処理能力
◆最終処分場所の所在地
◆最終処分方法
◆最終処分施設の処理能力
③収集運搬と処分をひとつの業者に委託する場合
◆①および②の記載事項をあわせて明記
マニフェストについて
排出事業者が廃棄物処理を委託する場合には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で管理することが法律で義務付けられています。 マニフェスト制度は、排出事業者が委託した産業廃棄物の移動や処理状況を把握し、不適切な処理や不法投棄を防止することを目的として1990年に導入されました。
紙マニフェスト
紙マニフェストは7枚綴りの複写式伝票で構成されています。排出事業者は、「廃棄物の種類・数量」「収集運搬業者名」「処分業者名」などを記入し、廃棄物とともに収集運搬業者へ交付します。各段階で収集運搬や処分が終了すると、記入済みの伝票が排出事業者へ戻ってきます。最終的に排出事業者の手元には4枚が残り、この伝票は受領日から5年間保存する義務があります。
電子マニフェスト
電子マニフェストは、紙マニフェストに記載する情報をインターネット上でやり取りできる仕組みです。排出事業者・収集運搬業者・中間処分業者・最終処分業者がシステムを通じて情報を登録するため、処理状況をリアルタイムで確認できる利点があります。
紙の保存や報告書提出が不要となり、業務負担の軽減につながります。ただし、利用にはすべての関係業者が電子システムを導入していることが前提で、導入費用も発生します。
また、「引き渡し日」「運搬終了日」「処分終了日」から3日以内に情報処理センターへの報告が義務付けられています。
石綿(アスベスト)について
石綿(アスベスト)は、平成18年(2006年)9月から「製造」「輸入」「使用」が禁止されています。かつては建材などに広く使われていましたが、吸入するとじん肺・肺がん・中皮腫などの原因となる可能性があるため、現在は厳しい規制が設けられています。建築物の解体や改修工事では、作業員のばく露防止や大気中への飛散防止のため、適切な対策が義務付けられています。
規制強化の経緯
令和2年10月1日施行
◆ケイ酸カルシウム板第1種を切断等する場合の措置新設
◆石綿含有成形品に対する措置の強化(切断等原則禁止)
令和3年4月1日施行
◆事前調査方法の明確化
◆分析調査を不要とする規定の吹付け材への適用
◆事前調査及び分析調査結果の記録等
◆計画届の対象拡大
◆負圧隔離を要する作業に係る措置の強化
◆仕上塗材を電動工具を使用して除去する割合の措置の新設
◆労働者ごとの作業の記録項目の追加
◆作業実施状況の写真等による記録の義務化
◆発注者による事前調査・作業状況の記録に対する配慮
令和4年4月1日施行
◆解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設
令和5年10月1日施行
◆事前調査・分析調査を行う者の要件新設
建築物石綿含有建材調査者
令和5年10月以降の工事では、事前調査は有資格者である「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
◆特定建築物石綿含有建材調査者
◆一般建築物石綿含有建材調査者
◆一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部限定)
◆令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
事前調査とは
工事前に建材に石綿が含まれているかを調査することです。
◆設計図書等の文書確認
◆現地での目視確認(製品情報の確認を含む)
「石綿なし」と証明できない場合は、分析調査を行うか石綿ありとみなすのが原則です。
石綿ありとみなして適切な対策を講じれば、分析調査は不要です。
調査結果の保存・掲示
◆調査結果は3年間保存
◆工事現場に写しを備え付け、概要を見やすい場所に掲示
◆記録項目例
・事業者名・住所・電話番号、現場住所、工事名称・概要
・事前調査終了日
・着工日、構造、調査方法・結果(石綿有無と根拠)
・目視確認が困難な材料の有無・場所
労働基準監督署への届出
石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
対象工事
①解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
②請負金額が100万円以上の特定の工作物の解体工事
③請負金額が100万円以上の建築物・特定の工作物の改修工事
届出事項
◆事業者情報、現場住所、工事名称・概要
◆調査終了日、工事期間
◆上記①の工事の場合は床面積の合計、②と③の場合は請負代金の額
◆建築物や工作物の構造、事前調査の実施部分、調査方法、調査結果(石綿の使用の有無とその判断根拠)
◆調査者氏名・証明書類の概要(建築物の場合)
◆石綿作業主任者の氏名(石綿が使用されている場合)
注意点
◆複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が請負事業者に関する内容も含めて報告する必要があります。
◆平成18年9月1日以降に着工した工作物について、同一の部分を定期的に改修する場合は、一度報告を行えば、同一部分の改修工事については、その後の報告は不要です。
建設発生土の搬出先の明確化について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を受けて、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。これにあわせて「資源有効利用促進法省令」も改正され、建設工事で発生する土砂(建設発生土)が適切に利用・処分されるよう、新たな義務が設けられています。具体的には、搬出先が盛土規制法に基づく許可地であるかどうかの確認や、搬出後の土砂受領書等の確認が求められます。
工事において建設発生土を搬出・搬入する場合には、次のような手続きや管理が必要となります。
再生資源の搬入や指定副産物の搬出前に行うこと
◆契約の際には、運搬費など処理にかかる経費の見積もりを適切に行うよう努めること。
◆再生資源利用促進計画・再生資源利用計画(以下「計画」)を作成すること。
一定規模以上の工事では計画を作成が必要
◆再生資源利用促進計画(搬出の計画)
・土砂 500㎥以上
・コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材 合計200t以上
◆再生資源利用計画(搬入の計画)
・土砂 500㎥以上
・砕石 500t以上
・加熱アスファルト混合物 200t以上
搬出の際に確認すべきこと
建設発生土を搬出する場合には、あわせて「確認結果票」を作成する必要があります。内容は次のとおりです。
◆搬出先が盛土規制法の許可地など、適正であることの確認
(盛土規制法・土砂条例・その他法令による許可や届出が行われているか)
◆発注者などが実施した土壌汚染対策法等に関する手続きの状況の確認
計画書の提出・掲示
作成した計画書は発注者へ提出して内容を説明するとともに、工事現場の見やすい場所に掲示します。
運送事業者への通知と管理体制の整備
計画内容を運送事業者に通知し共有するとともに、工事現場に責任者を置き、計画に基づく業務が適切に行える管理体制を整備します。
建設発生土の搬入・搬出後の確認
◆建設発生土を搬出先へ搬出したときは、受領書の確認を受けてください。
◆受領書の写しを工事完成後5年間保存してください。
◆搬出先が計画書と一致することを確認してください。
◆建設発生土を他の建設工事やストックヤードから受入れたときは、搬入元に受領書を交付してください。
建設工事の完成後に行うこと
計画の実施状況の記録・保存
◆元請業者は、計画の実施状況を把握して記録し、受領書の写しと合わせて5年間保存すること
◆発注者から請求があったときは、計画の実施状況を発注者に報告すること
建設発生土の最終搬出先の記録・保存
◆元請業者は建設発生土が計画に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに搬出先の名称や所在地、搬出量等を記載した書面を作成し、保存すること
◆他の搬出先へ搬出されたときも同様である
◆ただし、①~④に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要である。
①国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの)
②他の建設現場で利用する場合
③ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード
④土砂処分場(盛土利用等し再搬出しないもの)
令和6年6月以降の変更点
令和6年6月からは、ストックヤードに搬出した場合でも最終搬出先まで確認を行うことが義務づけられます。国に登録されたストックヤードに搬出した場合は、最終搬出先までの確認を行うことが不要となります。ストックヤードとはそのまま利用が可能な良質土、普通土を一時的に仮置きし、その後他の工事現場へ搬出して再利用するための施設です。

建設業にかかわることでしたらどんなご質問でも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。