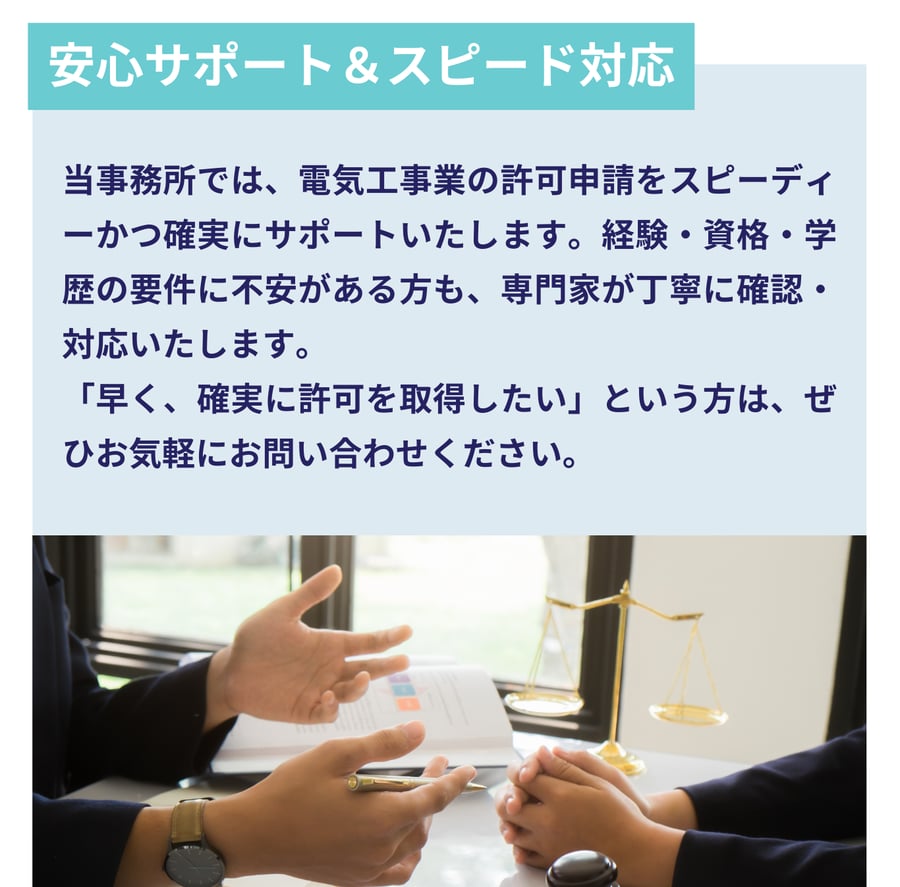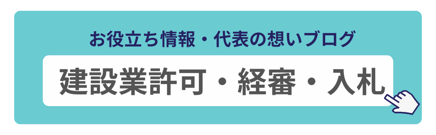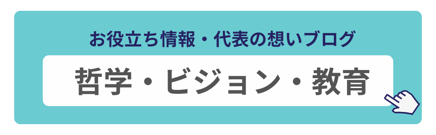営業所技術者 電気工事業

他の業種は10年の実務経験を証明することで、営業所技術者になることができますが、電気工事業は実務経験のみで営業所技術者になることができません。電気工事の場合は、建設業法だけでなく電気工事士法という法令も遵守しなければならないからです。電気工事士法については後ほどご案内いたします。
営業所技術者になるための国家資格等
特定建設業における営業所技術者の要件
◆1級電気工事施工管理技士
◆建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
◆建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
◆電気電子・総合技術監理「電気電子」
一般建設業における営業所技術者の要件
◆1級電気工事施工管理技士
◆2級電気工事施工管理技士
◆建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
◆建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
◆電気電子・総合技術監理「電気電子」
◆第1種電気工事士
◆第2種電気工事士 ※合格後3年以上の実務経験が必要
◆電気主任技術者(第1種~第3種) ※合格後5年以上の実務経験が必要
◆建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
◆計装 ※合格後1年以上の実務経験が必要
◆登録電気工事基幹技能者
◆登録送電線工事基幹技能者
電気工事士法(電気工事士)について

電気工事士の資格が不要な「軽微な工事」とは
電気工事士法では、電気工事を行うには資格が必要ですが、例外として「軽微な工事」にあたる場合は資格が不要です。具体的には、次のような工事が該当します。
600V以下の差込みプラグやソケット等への接続工事
コードやキャブタイヤケーブルを、差込み接続器・ソケット・ローゼット・スイッチなどに接続する工事。
電気機器や蓄電池の端子へのねじ止め工事
600V以下の電気機器や蓄電池に、コードやケーブルをねじ止めで接続する工事。
電力量計やヒューズの取付・取外し
600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズの設置や取外し。
小型変圧器(二次電圧36V以下)の二次側配線工事
電鈴・インターホン・火災感知器・豆電球などに使う小型変圧器(二次電圧36V以下)を使った配線工事。
電線を支持する柱や腕木などの設置・変更工事
地中電線用の管や暗渠の設置・変更工事
電気工事士について
第一種電気工事士ができること
第一種電気工事士免状を取得すると、電気工事士法で定められた次の工事に従事することができます。
自家用電気工作物の電気工事
最大電力500kW未満の需要設備に関する工事(ただし一部制限あり)。
一般用電気工作物の電気工事
住宅や事務所などに設置される一般的な電気設備に関する工事。
ただし、自家用電気工作物の工事のうち ネオン工事 や 非常用予備発電装置工事 を行う場合は、「特種電気工事資格者」の認定証が別途必要です。
また、工場やビルなどで最大電力500kW未満の需要設備を扱う事業所に従事している場合、事業主が産業保安監督部長へ申請し許可を受ければ、その事業所の 電気主任技術者 に選任されることも可能です。(手続きは事業主が行います。)
第一種電気工事士免状未取得者(試験合格者)ができること
試験に合格していても免状を取得していない場合は、「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けることで、一定範囲の工事に従事できます。
簡易電気工事
自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満かつ電圧600V以下で使用する電気工作物に関する工事。
また、工場やビルなどで最大電力500kW未満の需要設備を扱う事業所に従事している場合は、事業主の申請により 電気主任技術者 として選任されることも可能です。(こちらも手続きは事業主が行います。)
第二種電気工事士ができること
第二種電気工事士は、次のような電気工事に従事することができます。
一般用電気工作物等の工事
一般住宅や小規模な店舗・事務所など、電力会社から低圧(600V以下)で受電する場所の配線や電気使用設備の工事が可能です。
簡易電気工事に従事するためには
免状取得後、そのままでは「一般用電気工作物等」の工事のみ可能ですが、次の条件を満たすと 「簡易電気工事」 にも携わることができます。
・電気工事の実務経験を 3年以上 積む
・または 認定電気工事従事者認定講習 を受講し修了する
その上で、産業保安監督部長から 「認定電気工事従事者認定証」 が交付されると、以下の範囲が追加されます。
・自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満・600V以下で使用する電気工作物 の工事
電気主任技術者になるために
さらに、最大電力500kW未満の需要設備を持つ事業所(工場やビルなど)で働く場合、事業主が申請を行い産業保安監督部長の許可を得れば、第二種電気工事士でも 電気主任技術者に選任されることが可能 です。
(※手続きは事業主が行います)
免状について
令和3年4月1日以降に第一種電気工事士の免状交付申請を行う場合、3年以上の実務経験が必要です。(もともとは5年の実務経験が必要でした。) 第二種電気工事士については試験に合格して申請をすれば免状を受けることができます。