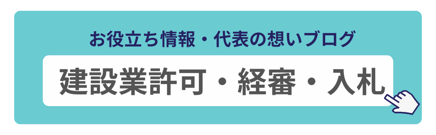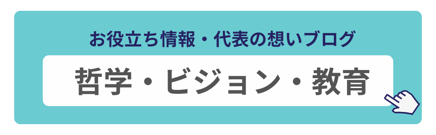資材置場への農地転用サポート

使っていない農地を資材置場として活用しませんか?
「相続で農地を引き継いだけれど、管理が大変」
「自宅から遠く、なかなか手が回らない」
「農業を続ける予定がない」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
使われていない農地は、地元の建設会社様の資材置場として有効活用できる可能性があります。
よくあるお悩み
農地を所有されている方
◆相続で引き継いだが、草刈りや管理が負担になっている
◆子どもが農地を引き継ぎたがらない
◆農地を貸していたが、借り手の農家が高齢でやめてしまった
建設業者様
◆資材置場が不足している
◆借りている土地が手狭になってきた
◆コストを抑えて資材置場を確保したい
弊所にご依頼いただくメリット
◆市役所・農業委員会での事前調査を代行
◆青地・白地など法的な制約を確認し、可能性を整理
◆建設会社とのマッチングや契約手続きもサポート
土地の場所をお知らせいただくだけで調査を開始できます。
ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
資材置場としての活用が選ばれる理由
◆建築物を建てないため、活用のハードルが比較的低い
◆荒れた農地を整備してもらえるため、管理の手間が減る
◆借り手からの賃料収入が得られる
資材置場で置かれるものの例
トラックや重機、骨材(砂利等)、仮設材(足場材等)など
よく聞く「青地」と「白地」とは?
市街化調整区域や用途地域外の農地は、一般的に「青地」と「白地」に分けられます。
◆青地 … 農業振興地域の農用地区域として定められている土地。農業を守るため、転用には厳しい制限があります。
◆白地 … 農用地区域外の土地。青地に比べて制限が少なく、資材置場などへの転用がしやすいエリアです。まずは、お持ちの農地が青地か白地かを確認することが、活用の第一歩になります。
「除外」とは?
青地を資材置場として使うには、まず「除外申請」が必要です。これは、農用地区域から土地を外すための手続きです。
◆受付は年に1回だけ、数週間程度(市町によって期間が異なります)
◆申請から完了までは約8か月かかります
たとえば浜松市では例年7月下旬~8月上旬の2週間、磐田市は6月いっぱい、袋井市は8月いっぱいなど、市町ごとにスケジュールが決まっています。この時期を逃すと、次の受付は半年以上先になってしまいますので、早めの準備が大切です。
「農転」とは?
白地であれば「農地転用許可申請(農転)」から手続きが始められます。毎月申請を受付しており、申請から許可まではおおよそ1か月で進みます。
青地であっても、緊急に必要な場合には「一時転用」という制度があります。これは短期間だけ資材置場として使うことができる制度で、工事終了後は速やかに農地へ戻すことが条件となります。
例:下水道工事で、3か月だけ資材置場として使用する場合など。
農地転用の手続きとスケジュール
青地
除外申請(約8か月) → 農転許可申請(約1か月) → 整地・利用開始 → 完了報告(約1か月)
白地
農転許可申請(約1か月) → 整地・利用開始 → 完了報告(約1か月)
一時転用
一時転用許可申請(約1か月) → 整地・利用開始 → 復旧 → 完了報告(約1か月)
ご依頼の流れ



活用事例(お客様の声)
数年前に親の相続で市街化調整区域の土地を取得しました。土地は農地となっていますが、私はサラリーマンで市街化区域に一戸建住宅を購入して住んでおり、農業はいたしておりません。規制があるようで、他に活用法が見つからないのでそのままにしていました。しかし放っておくと、雑草が生えて近隣にも迷惑がかかるため、折を見て週末に草取りに通っていました。
そんな時に「資材置き場として借りたい」と建設会社からお話をいただき、行政書士さんに農地転用などの手続きをしていただきました。今では、面倒な草取りからも解放され、毎月賃料もいただくことができ、とても助かっています。
(静岡県浜松市在住 A様)
まずはご相談ください
農地転用には専門的な手続きが必要ですが、初めての方でも大丈夫です。
「活用できるかどうか調べてほしい」という段階からお任せいただけます。