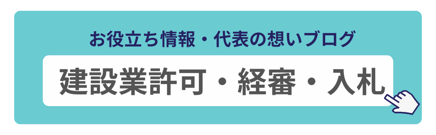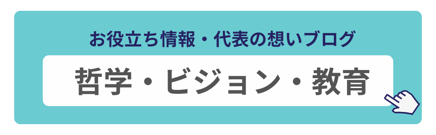建設業法 条文解説
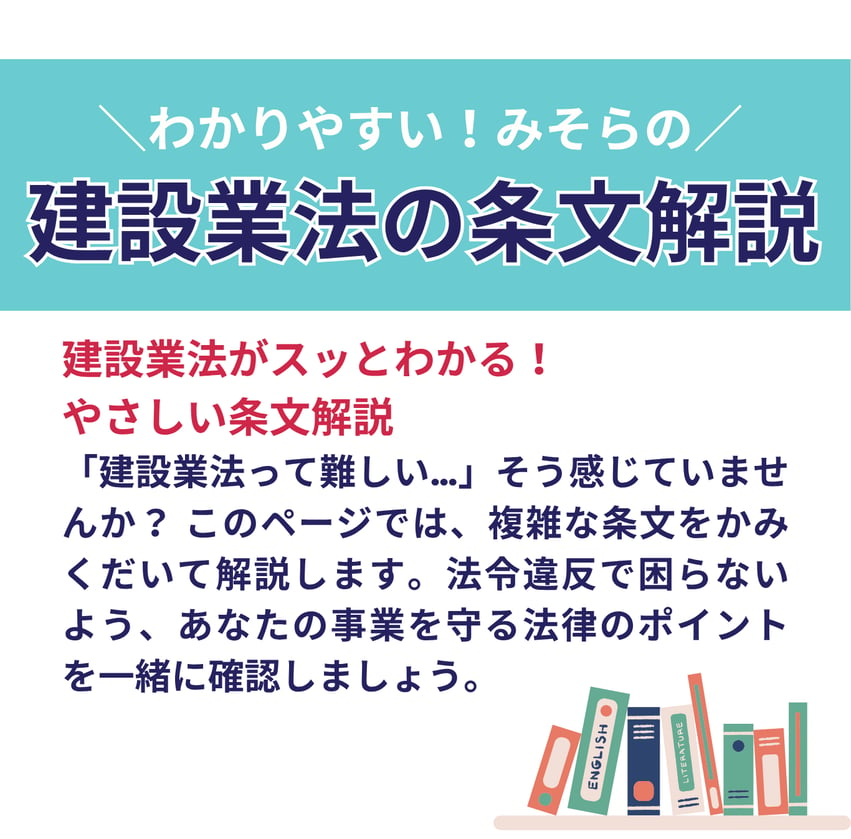
(第1条・第2条)
(第3条~第17条の3)
(第18条~第24条の8)
(第25条の27~第27条の40)
(第28条~第32条)
(第39条の4~第44条の3)
(第45条~第55条)
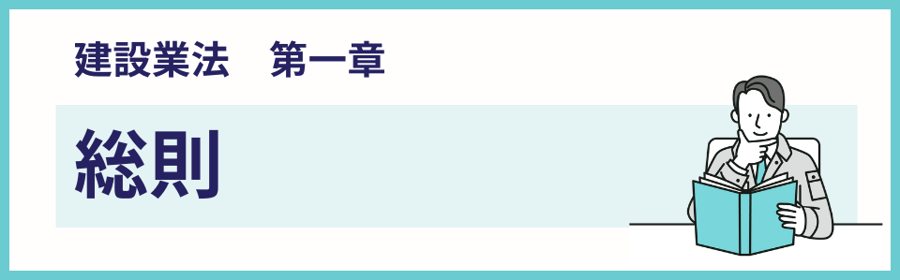
第一条(目的)
第1条 建設業法とは?
この法律は、建設業に携わる人々の技術や能力を高めるとともに、工事の契約を公正で適切なものとすることで、建設工事が安全かつ確実に行われることを目的としています。また、工事を発注する人を守り、建設業界全体の健全な発展を促進し、最終的には社会全体の安心と利益につなげることを目指しています。
第二条(定義)
第2条 用語の意味
◆建設工事: 道路や橋などの土木工事、建物を建てる建築工事など、この法律で定められた29種類の工事を指します。
◆建設業: 元請けや下請けといった立場にかかわらず、名称に関係なく「建設工事を完成させること」を引き受ける事業のことです。
◆建設業者: 国や都道府県から建設業の許可を受けて、建設業を営んでいる人や会社をいいます。
◆下請契約:ある建設工事を請け負った建設業者が、その工事の全部または一部を、別の建設業者に依頼する契約のことです。
◆発注者・元請負人・下請負人:工事を直接依頼する人を「発注者」といい、下請契約を依頼する側の建設業者を「元請負人」、その工事を引き受ける側の建設業者を「下請負人」といいます。
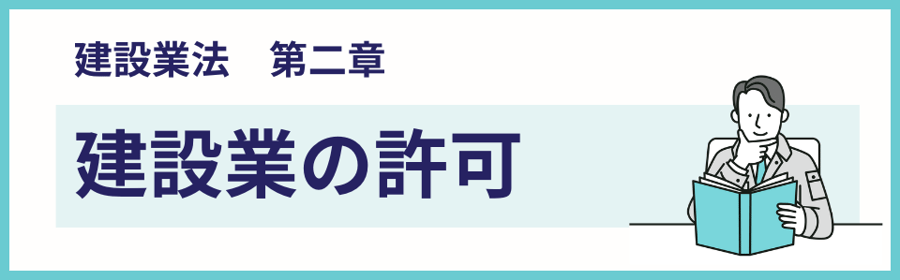
第三条(建設業の許可)
第3条 建設業を始めるには「許可」が必要です
建設業を営もうとする人や会社は、事前に「許可」を受けなければなりません。どこで許可を受けるかは、営業所をどこに置くかによって変わります。
複数の都道府県に営業所がある場合
→国土交通大臣の許可
1つの都道府県内にだけ営業所がある場合
→営業所がある地域を管轄する都道府県知事の許可
「営業所」とは、本店や支店など、実際に営業活動を行う場所をいいます。小規模な工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合は、許可を受けなくても建設業を営むことができます。
軽微な工事とは?
建築一式工事の場合
次のいずれかに当てはまれば、軽微な工事とされます。
・工事1件の契約金額(消費税込)が 1,500万円未満
・木造住宅で、建物の延べ面積が 150㎡未満
建築一式工事以外の場合
工事1件の契約金額(消費税込)が 500万円未満 の場合、軽微な工事とされます。「契約金額」は、消費税を含めた総額で判断します。また、注文者から支給された材料がある場合は、その材料の価格も含めて判断されます。
具体例
・工事代金(消費税込)…440万円
・注文者からの材料支給…100万円
この場合、合計で 540万円のため、建設業許可が必要となります。
建設業許可の更新について
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新をしないまま5年が経過すると、許可の効力はなくなってしまいます。
更新申請中の取扱い
更新の申請をしたけれど、まだ審査が終わっていない場合、審査結果が出るまでは、これまでの建設業許可がそのまま有効になります。
新しい許可の有効期間
更新許可が出た場合、その有効期間は「前の許可の期限が切れた日の翌日」から5年間です。
一般から特定に切り替えた場合
同じ業種で特定建設業許可を新たに取ったときは、それまでの一般建設業許可は、自動的に効力を失います。
第三条の二(許可の条件)
第3条の2 許可の条件について
建設業の許可を与えるとき、国土交通大臣や都道府県知事は、必要に応じて条件をつけることができます。また、その後に条件を変更することも認められています。
この条件は、建設工事が適切に行われることや、工事を依頼する人(発注者)を守ることを目的とした、必要最低限の内容に限られます。したがって、許可を受ける人にとって、不当に重い負担となるような条件を課すことはできません。
第四条(付帯工事)
第4条 付帯工事について
建設業者は、自分が許可を受けている工事を請け負うとき、その工事を完成させるために必要となる他の種類の工事についても、あわせて請け負うことができます。
第五条(許可の申請)
第5条 許可申請の手続き
建設業許可を受けたい人は、国土交通省令で定められた方法に従い、必要な情報を記載した申請書を提出しなければなりません。どこに提出するかは、営業所の場所によって異なります。複数の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に提出します。一つの都道府県にのみ営業所を置く場合は、その営業所がある都道府県の知事に提出します。
申請書に記載する内容
・会社や個人の名前
・営業所の名前と住所
・法人の場合:会社の資本金(出資金の合計も含む)と、役員などの氏名(業務を実質的に支配する立場の人全般を指します)
・個人事業主の場合:本人の氏名と、支配人がいればその氏名
・各営業所に配置する技術者の氏名(この法律で定められた資格を持つ人)
・許可を受けたい建設業の種類
・他に事業を行っている場合は、その事業の種類
第六条(許可申請書の添付書類)
第6条 添付書類について
許可申請書には、国土交通省令で定められた以下の書類を添付する必要があります。
・これまでの工事の履歴をまとめた書類
・過去3年間の各年度における工事の請負金額を記載した書類
・現在の従業員数を示す書類
・申請者本人(法人の場合は会社とその役員など、個人事業主の場合は本人)や、法定代理人が、許可が認められない基準に該当しないことを誓約する書類
・許可に必要な基準を満たしていることを証明する書類
・上記以外で、国土交通省令で定められたその他の書類
※許可の更新申請の場合は、工事経歴書、工事施工金額、使用人数の書類は添付不要です。
第七条(許可の基準)
第7条 4つの許可基準
建設業の許可は、申請者が以下のすべての基準を満たしている場合に限り与えられます。
事業を適切に経営・管理できる能力があること
会社の経営や業務全体をきちんと管理できる体制が整っている必要があります。例えば、法人であれば取締役に5年以上在籍していることなどが該当します。
営業所に「営業所技術者」を配置していること
国家資格や一定の実務経験がある人。例えば一級土木施工管理技士などです。
契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないこと
申請者本人や役員などが、過去に契約違反や不正をしたことがあり、今後もそのおそれがあると認められる場合には許可されません。
請負契約をきちんと実行できるだけの財産や信用があること
財産的な基盤や信用が明らかに不足している場合は、許可されません。
第八条(欠格要件)
第8条 許可を受けられない場合
建設業の許可は、申請者が以下のいずれかに該当する場合、与えられません。また、申請書や添付書類に重要な虚偽記載や記載漏れがある場合も許可されません。
①破産手続き中で、まだ権利を回復していない人
②過去に建設業の許可を取り消され、5年が経過していない人
③許可取り消し通知を受けた後、その処分が決まるまでの間に廃業などを届け出て、その届出から5年が経っていない人
④前号の期間内に廃業届などが出された際、その通知の60日以内に当該法人の役員などであった人、または個人の政令で定める使用人であった人で、その届出から5年が経っていない人
⑤営業停止命令の期間がまだ終わっていない人
⑥許可を受けようとする建設業について、営業を禁止されている期間が終わっていない人
⑦禁錮以上の刑を受け、刑期を終えるか、刑の執行を受けなくなってから5年が経っていない人
⑧建設業関連の法律や刑法、暴力団排除法などに違反して罰金刑を受け、刑期を終えるか、刑の執行を受けなくなってから5年が経っていない人
⑨暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年が経っていない人
⑩心身の病気などで、適切に建設業を営むことができないと国土交通省令で定められた人
⑪未成年者で、事業に必要な能力を持たない場合、その法定代理人(保護者など)が上記のいずれかに該当する人
⑫法人の役員や、政令で定める使用人のうち、上記のいずれかに該当する人がいる法人
(ただし、その人が許可取り消しや営業禁止などを受ける前から、当該法人の役員などで、その責任が限定的な場合は除きます)
⑬個人の政令で定める使用人のうち、上記のいずれかに該当する人がいる個人事業主
(ただし、その人が許可取り消しや営業禁止などを受ける前から、当該個人の政令で定める使用人であった場合で、その責任が限定的な場合は除きます)
⑭暴力団関係者がその事業活動を実質的に支配している場合
第九条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可換えについて
建設業の許可を持っている人が、事業所の移転などで新しい種類の許可が必要になった場合(事業承継による場合は除く)、新たに国土交通大臣または都道府県知事の許可を取得すると、以前の許可は効力を失います。具体的には以下のようなケースがあります。
ケース1
大臣許可→知事許可
例えば、以前は東京都と神奈川県に営業所があり大臣許可を受けていたが、営業所が東京都のみになった場合です。
ケース2
知事許可→他県の知事許可
例えば、東京都にあった営業所を神奈川県に移した場合です。
ケース3
知事許可→大臣許可
例えば、東京都だけにあった営業所に加えて神奈川県にも営業所を開設した場合です。
第十条(登録免許税及び許可手数料)
第10条 審査にかかる費用の支払い
国土交通大臣の許可を受ける場合、申請内容に応じて登録免許税や許可手数料の支払いが必要です。新規に許可を受ける場合は登録免許税を納めます。すでに持っている許可を更新する場合や、別の種類の許可を追加で受ける場合は、許可手数料を納めます。また、都道府県知事の許可を受ける場合は、申請手数料を納める必要があります。金額は都道府県ごとに異なります。
第十一条(変更等の届出)
第11条 届出の期限
建設業の許可を持っている者は、会社や営業所、役員、技術者などの情報に変更があった場合、または経営能力や技術者配置の基準を満たさなくなった場合、国土交通省令で定められた期限内に、必要な書類を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。
具体的には、申請時に提出した情報(会社名、営業所、役員、技術者など)に変更があった場合は30日以内、事業年度終了後の工事経歴や請負金額などは4か月以内、その他従業員数などの変更も同じく4か月以内、新しい技術者の配置や欠格要件に該当した場合は2週間以内に届出が必要です。
第十二条(廃業等の届出)
第12条 廃業の届出
建設業の許可を持つ事業者が廃業する場合は、状況に応じて、関係する方が30日以内に国土交通大臣または都道府県知事に届け出る必要があります。
個人事業主が亡くなり、事業の引き継ぎが行われなかった場合は、相続人が届け出ます。
法人が合併によって消滅し、その合併後に存続または新設される法人への事業承継が認められなかった場合は、その元役員だった人が届け出ます。
法人が破産手続きの開始決定により解散した場合は、破産管財人が届け出ます。
法人が合併や破産以外の理由で解散した場合は、清算人が届け出ます。
事業自体をやめた場合(事業承継が認められた場合を除く)は、その元個人事業主や元法人の役員が届け出ます。
第十三条(提出書類の閲覧)
第13条 公開される書類
建設業の許可に関わる書類は、国土交通大臣や都道府県知事が設置する「閲覧所」で、一般の方も自由に確認できるようになっています。
閲覧できる書類
◆許可申請書
(建設業の許可を申請するときに提出する書類)
◆会社の体制に関する書類
(経営業務の責任者や技術者など、許可を受けるために必要な人や組織が整っているかを示す書類)
◆会社情報などの変更を届け出る書類
(会社の名前や代表者が変わったときなどに提出する書類)
◆決算終了時に提出する書類
(事業年度が終わった後に提出する売上や利益などの情報が書かれた書類)
◆誓約書などの内容に変更があったときの届出書
◆上記以外で、国土交通省令で定められたその他の書類
第十四条(国土交通省令への委任)
第14条 申請手続きの詳細
建設業の許可を申請する際の具体的な手続きや必要書類の内容は、国土交通省令で定められています。
第十五条(許可の基準)
第15条 特定建設業の許可基準
特定建設業の許可を受けるには、国土交通大臣や都道府県知事が、申請者が以下の基準を満たしていると認める必要があります。
法令遵守や誠実性などに問題がないこと
第7条に当てはまる、つまり「法令を守り、誠実に事業を行う」ことができる人であることが必要です。
各営業所に「特定営業所技術者」を専任で配置していること
特定営業所技術者とは、技術検定や国家資格を持っている人、重要な工事で2年以上監督的立場の実務経験がある人、あるいは国土交通大臣に同等以上の能力があると認められた人です。
発注者から直接請け負う特定の高額な契約を履行できるだけの、十分な財産的な基盤があること
具体的には以下の条件をすべて満たしていることが求められます。
◆会社の損失が資本金の20%を超えていないこと
◆支払い能力が十分で、短期の借金に対して手元資金が足りること(流動比率75%以上)
◆資本金が2,000万円以上あること
◆純資産(資産から負債を引いた金額)が4,000万円以上あること
※純資産とは、資産から負債を引いた金額のことです。
第十六条(下請契約の締結の制限)
第16条 特定建設業許可が必要な下請契約
建設工事を直接発注者から請け負った場合でも、一部を下請けに出すことがあります。ただし、その下請契約の金額が大きい場合には、特定建設業の許可が必要です。
具体的には、元請負人として請け負った工事で、下請契約の金額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合です。また、一次下請業者が複数いる場合は、それぞれの下請契約の金額を合計して判断します。合計金額が基準を超える場合も、特定建設業の許可が必要となります。
第十七条(準用規定)
第17条 特定建設業にも適用されるルール
建設業には「一般建設業」と「特定建設業」がありますが、一般建設業の許可に関する多くのルールは、特定建設業にも同じように当てはまります。これを法律では「準用」と呼びます。
たとえば、許可申請のときに必要な書類や提出方法、欠格要件、営業所や技術者に関するルール、変更届や決算報告・廃業届の提出、そして書類を誰でも閲覧できる制度などは、一般建設業と同じルールが特定建設業にも適用されます。
ただし、特定建設業には一般建設業とは異なる条件や基準もあるため、条文の中の言葉が一部「特定建設業用」に置きかえられています。
たとえば、営業所に置く技術者は一般建設業では「営業所技術者」といいますが、特定建設業の場合は「特定営業所技術者」として読み替えられる、といった具合です。
第十七条の二(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
第17条の2 承継のルール
建設業を営んでいる法人や個人が、その建設業のすべてを他人に譲り渡す場合、条件を満たせば「建設業の許可」をそのまま引き継ぐこと(承継)ができます。
承継できないケース
次のような場合は、許可を引き継ぐことはできません。
◆譲渡する側が「一般建設業の許可」、譲り受ける側が「同じ業種の特定建設業の許可」を持っている場合
◆譲渡する側が「特定建設業の許可」、譲り受ける側が「同じ業種の一般建設業の許可」を持っている場合
これらの例外を除けば、譲渡人・譲受人の双方が事前に「認可」を受ければ、譲受人は譲渡の日からそのまま許可を引き継げます。
承継に必要な認可について
承継を行う場合は、許可の種類に応じて次の認可が必要です。
◆譲渡人が 国土交通大臣の許可 を受けている場合 → 国土交通大臣の認可が必要
◆譲渡人が 都道府県知事の許可 を受けている場合 → 原則としてその知事の認可が必要
ただし、以下の場合は大臣の認可が必要です。
◆譲受人が大臣の許可を持っているとき
◆譲受人が別の都道府県知事の許可を持っているとき
第十七条の三(相続)
第17条の3 個人建設業者が亡くなった場合の承継手続き
個人で建設業を営んでいた方が亡くなったとき、その相続人が事業を引き継いで続けるには、承継の認可を受ける必要があります。
申請期限
亡くなった日から 30日以内 に申請しなければなりません。
申請先
亡くなった方が 大臣許可 を受けていた場合 → 国土交通大臣へ申請
亡くなった方が 知事許可 を受けていた場合 → 原則として都道府県知事へ申請
事業継続の扱い
申請をすれば、認可が出るまでの間は仮に承継されたものとみなされる ため、事業がすぐに止まることはありません。その後、正式に認可を受けた相続人が、亡くなった方の建設業許可を引き継ぎ、これまでと同じように事業を続けることができます。
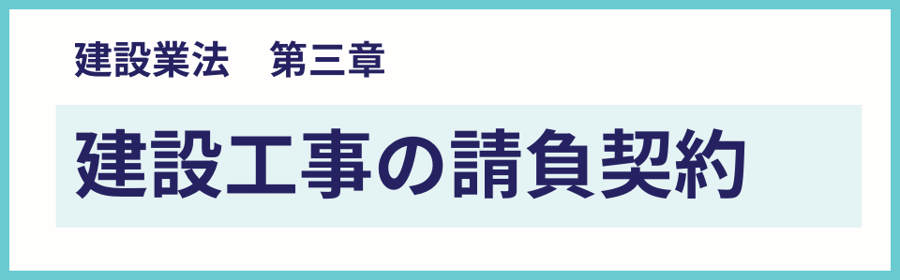
第十八条(建設工事の請負契約の原則)
第18条 建設工事契約の基本的な考え方
建設工事の請負契約を結ぶときは、発注者と受注者がおたがいに対等な立場で話し合い、内容に納得したうえで、公正な契約を結ぶことが基本の考え方です。契約を結んだあとは、おたがいが信頼の気持ちをもって約束を守り誠実に対応していくことが求められます。
第十九条(建設工事の請負契約の内容)
第19条 建設工事契約の記載内容
建設工事の契約を結ぶときには、重要な内容を契約書に書き込み、署名や押印をして、おたがいに書面を渡し合うことが必要です。記載する内容は次のとおりです。
①工事の内容
②請負代金の金額
③工事の開始時期と完成時期
④工事を行わない日や時間がある場合は、その内容
⑤前払い金や出来高払いがあるときは、その時期や方法
⑥設計変更や工事延期・中止があったときの対応
⑦天災などによる工期変更や損害の扱い方
⑧物価の変動による工事内容や金額の変更とその計算方法
⑨工事によって第三者に損害が出た場合の補償について
⑩資材や建設機械を発注者が提供する場合の内容や方法
⑪完成確認のための検査の時期や方法、引渡しの時期
⑫完成後の代金支払いの時期や方法
⑬品質が契約と合わなかった場合の責任や保証内容
⑭遅延・違約などがあったときの利息や損害金など
⑮契約に関するトラブルが起きた場合の解決方法
⑯その他、国が定めた必要な事項
契約内容に変更が生じた場合は、その変更についても書面に記載し、署名や押印をしておたがいに渡し合うことが必要です。書面の代わりに、電子契約などのITを使った方法をとることも可能です。国が定めた方法で、相手方の承諾を得たうえで行えば書面のやりとりと同じ効力があります。
第十九条の二(現場代理人の専任等に関する通知)
第19条の2 現場代理人の通知のルール
建設工事の現場では、請負者が配置する「現場代理人」と、発注者が配置する「監督員」がやりとりを行うことがあります。こうした役割を担う人を置くときには、その人の権限や、相手に意見や要望を伝える方法について、あらかじめ書面で通知することが義務づけられています。ただし、相手方の承諾があれば、書面ではなく電子メールや専用システムなどを使って通知することも可能です。
第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)
第19条の3 不当に安い契約をさせないために
発注者は、自分の立場を利用して、通常の費用では工事を行えないほど不当に安い金額で契約を結ばせてはいけません。この決まりは、建設業者が正当な利益を得られるようにし、いわゆる「買いたたき」を防ぐことを目的としています。たとえば「他ではもっと安くできるはずだ」と強い圧力をかけ、実際の原価を下回る金額で契約を迫るような場合がこれにあたります。
第19条の3 第2項 無理な安請け合いも禁止
建設業者自身も、正当な理由がないのに、工事にかかる通常の費用を下回る金額で契約を結んではいけません。たとえば、在庫として保有している安価な資材を使える場合など、工事費を抑えられる合理的な理由があるときは例外となりますが、そうした事情がないにもかかわらず、採算が取れないほど安い金額で仕事を引き受けることは認められていません。
第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
第19条の4 資材や機械の押し付けは禁止されています
発注者は、請負契約を結んだあとに、自分の立場を利用して工事に使う資材や機械、またはその購入先を指定し、請負業者に無理に買わせたり借りさせたりしてはいけません。たとえば「この資材は必ずこの会社から買ってほしい」「この機械を使いなさい」と一方的に指示し、通常より高い費用を負担させるような行為がこれにあたります。
この規定は、業者が不当に不利益を受けないようにし、自由で公正な取引関係を守るために設けられています。発注者による押しつけや、特定の業者との不透明な癒着を防ぐ役割もあります。
第十九条の五(著しく短い工期の禁止)
第19条の5 適正な工期を守るためのルール
発注者は、建設工事を依頼するときに、工事の内容に対して通常必要とされる期間よりも極端に短い工期を設定して契約することはできません。たとえば、本来2か月かかる工事を「1か月で終わらせてほしい」と無理に短縮させるような場合がこれにあたります。
このルールは、建設現場の安全や工事の品質を守るために設けられています。業者がしっかりと準備を行い、無理のない作業環境で工事を進められるようにすることが目的です。
第19条の5 第2項 業者側の無理な工期設定も不可
建設業者もまた、工事を完成させるために通常必要とされる期間に比べて、明らかに短すぎる工期で契約を結んではいけません。たとえ発注者から早期完成を求められた場合であっても、安全や品質を確保できないような無理な工期を受け入れることは認められていません。
第十九条の六(発注者に対する勧告等)
第19条の6 不当な契約違反に対する対応
発注者が、不当に安い請負代金を設定したり、資材や機械の購入先を業者に押しつけたりして、業者に不利益を与えた場合、国土交通大臣や都道府県知事は、発注者に対して「改善するように」と勧告を行うことができます。もし勧告に従わない場合には、その内容を公表することも可能です。
第二十条(建設工事の見積り等)
第20条 第1項 建設工事の見積り
建設業者は、工事の請負契約を結ぶにあたって、工事内容に応じた詳細な見積り(材料費等記載見積書)を作成するよう努めなければなりません。
見積書には、工事の種別ごとの材料費や労務費、現場で安全かつ適正に工事を行うために必要な経費の内訳を記載する必要があります。また、工事をどのような手順で進めるのか、工程ごとの作業内容や、その準備に必要な日数についても明らかにすることが求められています。
第20条 第2項 低額見積りの禁止
見積書に記載する材料費や労務費の金額は、通常その工事を行うために必要と認められる水準を著しく下回ってはいけません。
第20条 第4項 見積書を尊重した契約と交付義務
発注者は、請負契約を結ぶ際には、建設業者が作成した材料費や労務費などを記載した見積書の内容を尊重するよう努めなければなりません。また、建設業者は、発注者から求められた場合には、契約が成立する前までに、見積書を交付する必要があります。
第20条 第5項 電子データによる見積書の提供
見積書の交付は、発注者の承諾を得たうえで国が定める方法により電子データで見積内容を提供することができます。
第20条 第6項 著しく低い金額への変更要求の禁止
発注者は、見積書を受け取ったあと、その内容について、通常必要とされる材料費や労務費を大きく下回るような変更を求めてはいけません。
第20条 第7項 違反があった場合の行政による対応
もし発注者がこのルールに反して不当に低い金額への変更を求め、その内容で一定規模以上の工事契約が結ばれた場合、必要に応じて国土交通大臣や都道府県知事が発注者に対して勧告を行うことがあります。
第二十条の二(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等)
第20条の2 工期や費用に影響する可能性がある事象の情報共有
建設工事では、地盤の状態や資材価格の変動など、工期や費用に影響を与える可能性がある事柄があります。この条文では、契約前に発注者と建設業者が必要な情報をお互いに伝え合うことを定めています。
発注者は、土地の地盤状況など工事に影響しそうな情報を事前に伝える義務があります。建設業者も、資材価格の変動など工期や費用に影響が出そうな事柄を事前に知らせる必要があります。
さらに、契約後にこうした事象が発生した場合、建設業者は工期や費用の変更について協議を申し出ることができ、発注者は正当な申し出であれば誠実に協議に応じる努力をしなければなりません。
第二十一条(契約の保証)
第21条 前金払い時の保証ルール
建設工事の契約で、発注者が工事代金の一部または全部を前もって支払う場合、発注者は建設業者に対して保証人を立てることを求めることができます。ただし、公共工事の前払金保証制度の対象工事や、政令で定められた小規模工事では、この制度は適用されません。建設業者が保証を求められた場合、次のいずれかを用意する必要があります。
金銭的保証人
工事が途中で止まった場合などに、損害金を支払うことを保証する人や機関です。
別の建設業者による保証
建設業者に代わって工事を最後まで完成させることを保証する業者です。
もし建設業者が保証を用意できなければ、発注者は前金を支払わなくてもよいことになっています。
第二十二条(一括下請負の禁止)
第22条 一括下請けの禁止
建設業者は、自分が請け負った工事をまるごと他の業者に任せる(一括下請け)ことは禁止されています。また、下請けとして一括で工事を受けることも禁止です。
一括下請負は原則として禁止されていますが、民間工事であって、共同住宅の新築工事のように多数の人が利用する重要な建設工事(政令で定められたもの)に該当せず、なおかつ元請業者があらかじめ発注者から書面による承諾を得ている場合に限り、例外的に認められます。ただし、この特例は公共工事には適用されません。
さらに、書面による承諾の代わりに、発注者が電子的な方法(国土交通省令で定められた方式)で承諾の通知をすることもできます。この場合も、書面での承諾があったものとみなされます。
第二十三条(下請負人の変更請求)
第23条 不適当な下請業者の変更請求
発注者は、元請業者が選んだ下請業者のうち、工事の実施に著しく不適当だと判断される者がいる場合には、その下請業者の変更を求めることができます。ただし、事前に発注者が書面で承諾した下請業者については、変更を求めることはできません。書面の代わりに、電子的な方法(国が定めた方式)で承諾の通知がされていれば、書面と同じ効力があります。
第二十三条の二(工事監理に関する報告)
第23条の2 設計通りに工事できないときの報告
建築士から「設計図書どおりに工事をするように」と指摘を受けたにもかかわらず、それに従えない理由がある場合、その理由をすぐに発注者に報告しなければなりません。報告は、契約時などに定めた方法(書面や電子メールなど)に従って行う必要があります。
第二十四条(請負契約とみなす場合)
第24条 請負契約とみなされる場合
契約の名前が「委託」など別の表現でも、報酬をもらって建設工事を完成させることが目的の契約であれば、建設業法では請負契約として扱われます。つまり、契約書の名称ではなく、実際の内容が建設工事の請負にあたるかどうかが判断基準になります。
第二十四条の二(下請負人の意見の聴取)
第24条の2 下請負人の意見を聞く義務
元請業者は、工事の細かい工程や作業方法を決める前に、下請業者の意見をあらかじめ聞く必要があります。これは、下請業者の立場や現場の状況を考慮し、工事をスムーズに進め、適正な施工を行うためのルールです。
第二十四条の三(下請代金の支払)
第24条の3 下請代金の支払いのルール
元請業者は、下請業者が行った工事に対して、代金を受け取ったら1か月以内に、できるだけ早く支払う必要があります。特に、労務費にあたる部分は現金で支払うように配慮します。
また、前払金を受け取った場合は、下請業者が資材の購入や人員確保など工事準備をスムーズに行えるよう、前払金の一部を適切に支払うことが求められます。
第二十四条の四(検査及び引渡し)
第24条の4 下請工事の検査と引渡しルール
下請業者から「工事が完成した」と連絡を受けたら、元請業者はできるだけ早く、遅くとも20日以内に工事の検査を行う必要があります。
工事が完成していると確認できたら、下請業者から引渡しの申し出があった場合、特別な取り決めがない限りすぐに引き渡しを受けることが求められます。
ただし、契約で「工事完成予定日から20日以内の特定の日に引渡す」といった取り決めがある場合は、その内容が優先されます。
第二十四条の五(不利益取扱いの禁止)
第24条の5 下請け業者への不利益取扱いの禁止
下請業者が不正や法律違反を通報した場合、元請業者はその通報を理由に不利益な扱いをしてはいけません。
具体例:下請業者が、元請業者の違法行為を国土交通大臣や公正取引委員会、中小企業庁長官に報告した場合でも、報復的な扱いは禁止されています。
第二十四条の六(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第24条の6 下請代金の支払い期日
支払期日
特定建設業者が発注する下請契約では、代金は工事完成の確認日から50日以内に支払う必要があります。支払期日が事前に決められていない場合は、確認日から50日後が自動的に支払期日となります。
支払方法の制限
下請業者が金融機関で現金化しにくい手形での支払いは禁止されています。
支払のタイミング
出来形払いや完成払いを受けた日から1か月以内、または引渡し申出日から50日以内の早い方の日までに支払う必要があります。支払期日が決まっていない場合は、引渡し申出日から50日以内が支払期限です。
遅延利息
支払期日を過ぎた場合、遅延利息の支払い義務が発生します。利息額は国土交通省令で定められた率に基づき計算されます。
第二十四条の七(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第24条の7 法令遵守の指導と是正措置
下請業者への指導義務
特定建設業者は、自分が直接請け負った工事で、下請業者が建設業法や労働関係法令に違反しないよう、適切に指導する必要があります。
違反の是正
下請業者が法律違反をしている場合は、その内容を伝え、速やかに改善するよう求めます。
通報義務
指導しても違反が改善されない場合は、元請業者は国土交通大臣や都道府県知事、または工事現場を管轄する知事に通報しなければなりません。
第二十四条の八(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8 施工体制の透明性
施工体制台帳の作成義務
特定建設業者は、下請業者と契約を結び、その契約金額の合計が政令で定める金額を超える場合、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えておく必要があります。
台帳に記載する内容
◆下請業者の会社名
◆工事の内容と工期
◆その他国土交通省令で定められた事項
下請業者からの情報提供
下請業者がさらに他の業者に工事を任せた場合、その会社名や工事内容・工期などを、元請業者に知らせなければなりません。
閲覧義務
発注者から求められたときは、元請業者は施工体制台帳を閲覧できるようにしなければなりません。
施工体系図の掲示
特定建設業者は、国土交通省令で定められた方法で施工体系図を作成し、現場の見やすい場所に掲示する必要があります。
第二十五条(建設工事紛争審査会の設置)
第25条 建設工事紛争審査会とは
建設工事の請負契約に関して、トラブル(紛争)が起きたときに公正に解決するための場として建設工事紛争審査会が設けられています。審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争について、「あっせん」「調停」「仲裁」といった方法で解決図ります。
審査会には、国土交通省に設けられる中央建設工事紛争審査会と、各都道府県に設けられる都道府県建設工事紛争審査会の2つがあります。
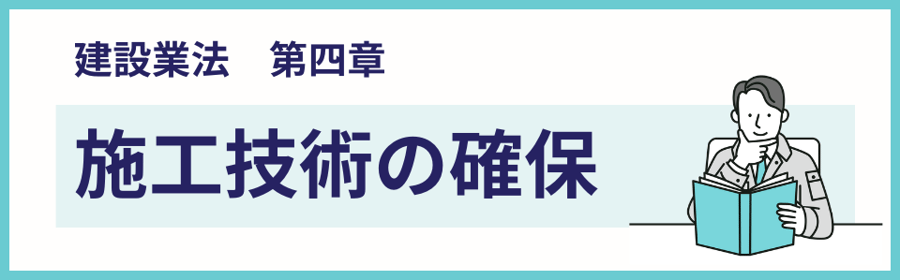
第二十五条の二十七(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
第25条の27 施工技術を守り育てる役割
建設業者は、建設工事を支える人材や技術を次の世代へつなぐ責任があります。人材の育成や確保、施工技術の維持・向上に取り組むことが求められます。
また、働く人の知識や技能を正しく評価し、それに見合った賃金を支払うことで、労働者が安心して働ける環境を整える必要があります。現場で働く人自身も、より良い工事を行うために知識や技能の向上に努めることが期待されています。
さらに、国は講習の実施や資料の提供などにより、こうした取り組みを後押しする支援を行います。
第二十五条の二十八(建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
第25条の28 ICTの活用について
特定建設業者は、工事を適切に進めるために、ICT(情報通信技術)を有効に活用することが求められます。工事の進捗管理システムを整えたり、必要な情報をリアルタイムで共有できる体制をつくることが例として挙げられます。
元請業者は、自社だけでなく下請業者もICTを活用できるよう、必要な指導や支援を行う努力をすることが必要です。
国土交通大臣は、ICTの活用が円滑に行われるよう、指針(ガイドライン)を定め、公表することになっています。
第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条 技術者の配置
建設業者は、工事現場ごとに工事を管理するための 主任技術者 を置く必要があります。また、発注者から直接請け負った規模の大きな工事では、主任技術者よりも高い資格を持つ 監理技術者 の配置が求められます。
公共性の高い重要な工事では、原則として主任技術者や監理技術者は 専任 で配置しなければなりません。ただし、工事金額や現場の状況、ICTの活用など、一定の条件を満たす場合には 兼任 が認められることもあります。
なお、専任の監理技術者となるためには、資格者証の交付を受け、必要な講習を修了していることが条件です。発注者から求められた場合には、資格者証を提示する義務があります。
第二十六条の二(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条の2 技術者の設置②
土木工事業や建築工事業の業者が、一式工事とあわせて他の専門工事を行う場合には、その工事を管理できる資格を持つ技術者を自社に配置するか、あるいはその工事の許可を持つ業者に依頼する必要があります。つまり、建設業者が自分の許可業種に関連する他の工事を行うときは、
◆必要な技術者を配置して自社で施工する
◆その工事の許可を持つ業者に任せる
このどちらかの対応を取らなければならない、という決まりです。
第二十六条の三(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条の3 主任技術者の兼任
通常、元請業者と下請業者は、それぞれの工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。
しかし「特定専門工事」の場合には、一定の条件を満たせば、元請業者の主任技術者が下請業者の分も兼任することができます。
特例を利用するための条件
◆元請・下請間で 合意書を取り交わす こと(主任技術者の氏名や工事内容など所定事項を明記)。
◆書面のほか、国土交通省令で定める電子的方法による合意も可能。
◆元請が合意を行うには、事前に 発注者の承諾(書面または電子的方法)が必要。
兼任できる主任技術者の要件
◆特定専門工事と同種の建設工事で 1年以上の指導監督経験 があること。
◆工事現場に 専任 で配置されていること。
(この場合、通常の「専任に関する規定〔第26条第3項〕」は適用されません。)
特定専門工事とは
◆土木一式・建築一式以外の工事で、技術が画一的で施工管理の効率化が求められるもの。
◆下請契約金額が政令で定める一定額未満である工事に限られる。
◆発注者から直接請け負った大規模工事などは対象外。
注意点
主任技術者の兼任により、下請業者が主任技術者を置かなくてもよい場合でも、その工事をさらに他の業者に 再委託(再下請)することはできません。
第二十六条の四(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第26条の4 主任技術者の職務
主任技術者や監理技術者は、工事を安全かつ円滑に進めるため、次のような役割を担っています。
◆施工計画の作成
◆工事の進行管理
◆品質を確保するための技術的管理
◆現場で働く人への指導・監督
これらを誠実に行うことが求められます。また、現場で働く人たちは、主任技術者や監理技術者の指導に従い、安全で品質の高い工事を実現するために協力することが必要です。
第二十六条の五(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
第26条の5 営業所技術者の特例
一定の条件を満たす小規模な工事では、現場に主任技術者や監理技術者を常駐させる代わりに、営業所にいる技術者がその職務を兼ねることが認められています。
特例が適用されるための条件
◆営業所が契約した工事であること
◆工事金額が政令で定めた上限未満であること
◆営業所と現場との連携体制が整っていること
◆ICTを活用して現場の状況把握や管理ができること
さらに、この特例を利用できるのは、担当する工事現場の数が政令で定める上限以内であり、兼任しても業務をきちんと遂行できると認められる範囲に限られます。
監理技術者を兼任する場合
営業所の技術者が監理技術者の職務を兼任するには、
◆監理技術者資格者証を持っていること
◆所定の講習を受講していること
が必要です。これは、専門的な知識と大きな責任を伴うためです。また、発注者から求められた場合には、資格者証を提示して自らの資格を証明しなければなりません。
第二十七条の二十三(経営事項審査)
第27条の23 経営事項審査
国や自治体などが発注する公共工事を直接請け負うためには、建設業者は事前に「経営事項審査(経審)」を受けなければなりません。この審査は、その会社が公共工事を安心して任せられるだけの経営基盤を持っているかどうかを判断する制度です。経審の対象となる工事の範囲は、政令で定められています。単なる書類確認ではなく、具体的な数値に基づいて評価が行われる点が特徴です。
評価の内容
審査で評価されるのは、大きく分けて次の2つです。
◆経営状況 … 財務内容など、会社の安定性を示すもの
◆経営規模・技術力など … 売上高や有資格技術者の数など、施工能力を示すもの
どの項目をどのように点数化するかは、国土交通大臣が中央建設業審議会の意見を踏まえて定めることになっています。
第二十七条の二十四(経営状況分析)
第27条の24 経営状況分析
経営事項審査の中でも「経営状況」の評価(財務内容など)は、登録経営状況分析機関 と呼ばれる、国土交通大臣に登録された専門機関が行います。
建設業者は、必要事項を記載した申請書を作成し、登録経営状況分析機関に提出します。申請書には、会社の経営状況を裏付ける資料(例:財務諸表など)を添付する必要があります。必要に応じて、分析機関から追加資料の提出や報告を求められることもあります。評価に用いる項目や採点方法は、国土交通大臣が中央建設業審議会の意見を踏まえて定めます。
第二十七条の二十五(経営状況分析の結果の通知)
第27条の25 経営状況分析の結果の通知
登録経営状況分析機関は、分析を行った後、速やかにその結果を建設業者に通知しなければなりません。通知の方法や細かい手続きについては、国土交通省令で定められています。通知されるのは、分析に基づいた「数値的な結果」です。建設業者はこの数値をもとに、経営事項審査の評価や準備を進めることになります。
登録経営状況分析機関一覧
◆(一財)建設業情報管理センター
◆(株)マネージメント・データ・リサーチ
◆ワイズ公共データシステム(株)
◆(株)九州経営情報分析センター
◆(株)北海道経営情報センター
◆(株)ネットコア
◆(株)経営状況分析センター
◆経営状況分析センター西日本(株)
◆(株)NKB
◆(株)建設業経営情報分析センター
第二十七条の二十六(経営規模等評価)
第27条の26 経営規模等評価の申請手続き
経営規模等評価を実施するのは、建設業の許可を出した国土交通大臣または都道府県知事です。
申請書の作成・提出
建設業者は、省令で定められた内容を記載した申請書を作成し、許可を出した大臣または知事に提出します。
添付書類の提出
申請書だけでなく、売上高や施工実績などを証明する書類も添付する必要があります。(具体的な書類の種類は国土交通省令で定められています。)
追加資料の求め
提出された書類だけでは情報が不足している場合など、審査に必要と認められれば、大臣または知事は追加の報告や資料の提出を求めることができます。
第二十七条の二十七(経営規模等評価の結果の通知)
第27条の27 評価結果の通知
評価を行った国土交通大臣または都道府県知事は、評価が完了したら遅滞なくその結果(数値)を申請した建設業者に通知します。
第二十七条の二十八(再審査の申立)
第27条の28 再審査の申立て
建設業者が通知された評価結果に異議があるときは、その評価を行った大臣または知事に対して再審査の申立てを行うことができます。
第二十七条の二十九(総合評定値の通知)
第27条の29 総合評定値の通知
建設業者が希望する場合、国や都道府県は総合評定値を通知しなければなりません。総合評定値とは、経営状況分析の結果、経営規模等評価の結果をもとに計算される、企業全体の客観的な評価値です。建設業者が総合評定値の通知を請求するためには、経営状況分析の結果(登録分析機関から通知された数値)を提出しなければなりません。
また、建設工事の発注者(国・地方公共団体など)は、特定の建設業者の総合評定値を請求することができます。
この場合、知事や大臣は、請求内容に応じて総合評定値を通知しなければなりません。(ただし、その建設業者がまだ自ら請求をしていない場合は、「経営規模等評価の数値」のみでも可)
第二十七条の三十(手数料)
第27条の30 手数料の支払い
経営事項審査において、国土交通大臣に申請や請求を行う場合には、手数料を支払う義務があります。具体的には、経営規模等評価の申請や、総合評定値の請求を国に対して行う場合に、その手続きに必要な実費を反映した政令で決められた手数料を支払う必要があるということです。
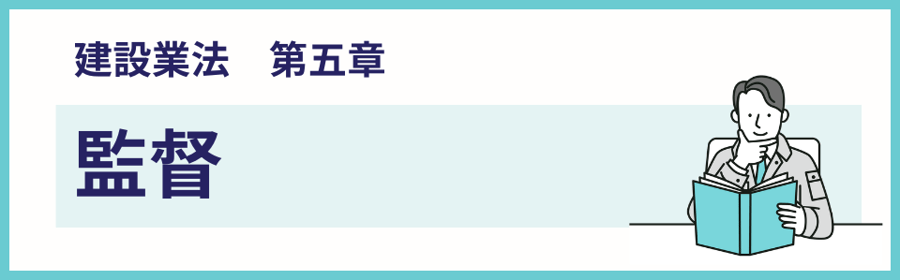
第二十八条(指示及び営業の停止)
第28条 指示・営業停止の措置
建設業者が法律違反や社会的に問題のある行為を行った場合、国や都道府県(知事)は、業者に対して指示や営業の停止などの措置をとることができます。
第一項:行政による指示・措置の対象
主に次のような場合が対象です。
◆工事の施工が雑で危険な場合
◆不誠実な取引を行った場合
◆法律違反(他の法律も含む)をした場合
◆帳簿や書類の管理が不十分な場合
◆技術者が重大な不適切対応をした場合
◆無許可業者や営業停止中の業者と契約した場合
◆住宅の瑕疵担保責任を果たさなかった場合
第二項:許可なく営業する者への指示
知事は、許可なく建設業を営む者が次の行為をした場合、必要な指示を出すことができます。
◆工事を適切に施工せず、公衆に危害を及ぼすおそれが高い場合
◆請負契約に関して著しく不誠実な行為を行った場合
第三項:営業停止の命令
国土交通大臣や知事は、以下の場合に、最長1年間、事業の全部または一部の停止を命じることができます。
◆許可を得て建設業を営む者が特定のルール違反をした場合、または指示に従わない場合
◆許可なく営業する者が前項の違反をした場合、または指示に従わない場合
第四・第五項:他の都道府県での営業
◆他の知事や大臣から許可を受けた業者でも、自分の都道府県内で問題がある場合、知事は指示を出せます。
◆知事は、ルール違反や指示不履行の業者に対して、最長1年間、その都道府県内で事業の全部または一部を停止させることができます。
第六項:処分の報告
営業停止などの処分を行った場合、処分を行った知事は速やかに、許可権限を持つ大臣や他の都道府県知事に報告・通知する義務があります。
第七項:発注者への勧告
国土交通大臣や知事は、必要と認めた場合、工事を発注した発注者に対しても、適切な対応を取るよう勧告することができます。
第二十九条(許可の取消し)
第29条 許可の取り消し①
国土交通大臣や都道府県知事は、許可を与えた建設業者が以下のいずれかの状況になった場合、許可を取り消さなければなりません。
必要な基準を満たさなくなった場合
例:経営業務の管理責任者がいなくなった
例:自己資本など財産的基盤が不足した
許可が本来与えられない状況に後から該当した場合
例:会社役員が特定の犯罪で刑罰を受けた
例:過去に不正行為で営業停止処分を受けた
二重許可や必要な別の許可がない場合
※他業者の事業を正式に引き継いだ場合は除く
事業を開始しない、または長期間休止した場合
例:許可取得後1年以内に事業を始めなかった
例:事業を始めたが1年以上続けて休止した
その他特定の事由に該当した場合
個人事業主の死亡に伴い承継が認められなかった場合
不正な方法で許可や承認を得た場合
例:虚偽の情報提出
例:承認手続きで不正を行った
悪質な違反行為や営業停止命令違反
営業停止中にも関わらず営業を続けた場合など
条件違反による取り消し
さらに、許可に際して付された条件に違反した場合も、国土交通大臣や知事は許可を取り消すことができます。
第二十九条の二(許可の取消し)
第29条の2 許可の取消し②
国土交通大臣や都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地が不明になったり、建設業者本人(法人の場合は役員、個人の場合は支配人を含む)の所在が確認できない場合、官報や都道府県の公報でその事実を知らせます。もしこのお知らせから 30日間 が過ぎても、建設業者から連絡や申し出がない場合には、許可を取り消すことができます。
第二十九条の三(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
第29条の3 許可取消後の措置
第一項
建設業の許可が失効した、営業停止命令を受けた、または許可が取り消された場合でも、その効力が失われる前や処分を受ける前に契約を結んだ工事だけは、引き続き施工できます。ただし、許可が失効したり処分を受けた2週間以内に、その事実を工事を依頼した注文者に必ず知らせなければなりません。
第二項
以前特定建設業者だった人やその事業を引き継いだ人が工事を続ける場合、特定建設業者に求められる下請契約の締結の制限(第十六条)は適用されません。
第三項
工事を続けられるとされているものの、国土交通大臣や都道府県知事は公共の利益のために特に必要だと判断した場合は、その工事を止めるよう命令することができます。
第四項
工事を続ける元建設業者やその事業を引き継いだ人は、その工事を完成させる目的の範囲内では、法律上「建設業者」として扱われます。
第五項
注文者は、上記の通知を受け取った日、または許可が失効したり処分があったことを知った日から30日以内であれば、その工事の請負契約を解除することができます。
第二十九の四(営業の禁止)
第29条の4 営業の禁止
第一項
国土交通大臣や都道府県知事が、建設業者に営業停止命令を出す場合、その業者だけでなく、関与した責任者も、同じ期間、新たに建設業の営業を始めることを禁止します。
◆法人の場合
その役員など、そして処分の原因となった事実について責任のある使用人
(処分前60日以内にその立場だった人も含む)
◆個人の場合
その本人、そして処分の原因となった事実について責任のある使用人
(処分前60日以内にその立場だった人も含む)
第二項
国土交通大臣や都道府県知事が、不正な手段による許可取得や営業停止命令への違反などの理由で建設業の許可を取り消す場合は、その業者だけでなく、関与した責任者も、5年間、新たに建設業の営業を始めることを禁止します。
◆法人の場合
その役員など、そして処分の原因となった事実について責任のある使用人
◆個人の場合
処分の原因となった事実について責任のある使用人
ただし、政令で定める軽微な工事のみを請け負う場合は除きます。
第二十九の五(監督処分の公告等)
第29条の5 処分の公告
第一項
国土交通大臣や都道府県知事が、営業停止命令、許可の取り消し、または所在不明による許可取り消しといった処分を行った場合、その内容を公示しなければなりません。
第二項
国土交通省と各都道府県には、それぞれ「建設業者監督処分簿」という記録が保管されます。これは、建設業者への行政処分を管理するためのものです。
第三項
処分を受けた建設業者については、処分日や内容など必要な情報を処分簿に記録しなければなりません。
第四項
処分簿は誰でも閲覧できるように公開されます。
これにより、建設業者の処分歴が透明になり、利用者が業者を選ぶ際の参考になります。
第三十条(不正事実の申告)
第30条 不正行為の通報
第一項:許可を受けた建設業者の場合
建設業者が許可を受けた上で違反行為をしている場合は、利害関係者は次の機関に通報できます。
◆許可を出した国土交通大臣
◆許可を出した都道府県知事
◆工事が行われている地域を管轄する知事
第二項:無許可で営業している場合
許可を受けずに建設業を営んでいる人が違反行為をしている場合も、利害関係者は工事が行われている地域を管轄する都道府県知事に通報し、適切な対応を求めることができます。
第三十一条(報告徴収及び立入検査)
第31条 報告と立入検査
第一項:報告の求め
国土交通大臣はすべての建設業者に対し、知事は自分の都道府県内で建設業を営む者に対し、建設業法の運用に必要な範囲で、事業の内容、財産の状況、工事の進み具合などについて報告を求めることができます。また、担当の職員に、営業所などの関係場所に立ち入って、帳簿や書類などを検査させることもできます。
第二項:立入検査
立ち入り検査を行う職員は、自身の身分を示す証明書を必ず持ち歩き、検査の対象となる関係者に提示しなければなりません。また、この立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために与えられたものとして解釈してはならないとされています。
第三十二条(参考人の意見聴取)
第32条 参考人の意見聴取
第一項:聴聞での意見聴取
建設業の許可を取り消すための聴聞を行う際、その聴聞を主宰する人は、必要だと判断した場合、参考人から意見を聞かなければなりません。
第二項:弁明の機会
前の条文の規定は、国土交通大臣や都道府県知事が、指導や営業停止命令、または営業禁止の処分を行う際に、関係者に弁明(言い分を述べる)の機会を与える場合にも適用されます。
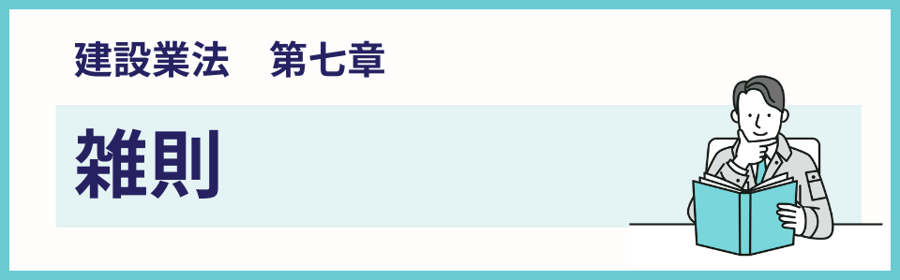
第三十九条の四(電子計算機による処理に係る手続の特例等)
第39条の4 電子申請について
国や都道府県(登録経営状況分析機関を含む)への手続きは、書面でなくても、国の定める方法に従って、電子データや磁気ディスクなどで提出することが認められています。
第一項:電子提出の認められ方
国土交通省令で定められた方法であれば、書面ではなく、磁気ディスク(またはそれに準じる確実な記録媒体)で提出することが認められています。
第二項:電子データの効力
電子データで行われた手続きは、書面で提出されたものとして扱われます。電子データでの提出であっても、この法律の規定(罰則を含む)が同様に適用されます。また、磁気ディスクに記録された内容は、書面に記載されたものとみなされます。
第四十条(標識の掲示)
第40条 掲げる標識の内容
建設業者は、自社の事務所と、直接請け負った工事現場の双方に、一般の人から見えやすい場所に標識を掲げる必要があります。標識には、国土交通省令で定められた方法に従い、許可を受けている建設業の種類や、一般建設業か特定建設業かの区別、その他必要な情報を記載します。
店舗に掲げる標識の内容
◆商号又は名称
◆代表者の氏名
◆一般建設業又は特定建設業の別
◆許可を受けた建設業の種類
◆許可番号
◆許可年月日
◆店舗で営業している建設業
建設工事現場に掲げる標識の内容
◆商号又は名称
◆代表者の氏名
◆技術者の氏名
・専任の有無
・資格名、資格者証交付番号
◆一般建設業又は特定建設業の別
◆許可を受けた建設業の種類
◆許可番号
◆許可年月日
第四十条の二(表示の制限)
第40条の2 表示の制限について
建設業を営む人は、許可を受けていないのにあたかも許可を受けた建設業者であるかのように、一般の人に誤解させるような表示をしてはいけません。
第四十条の三(帳簿の備付け等)
第40条の三 帳簿の備付けと保存
建設業者は、国土交通省令で定められた方法に従い、各営業所に事業に関する帳簿を備え付ける必要があります。また、その帳簿だけでなく、事業に関する書類や図書も保存しなければなりません。これは、事業活動を正確に記録し、管理するための義務です。
帳簿に記載すべき内容
①営業所の代表者の⽒名と就任⽇
②注⽂者と締結した建設⼯事の請負契約に関する事項
・請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
・注文者との契約日
・注文者の商号、住所、許可番号
・注文者による完成を確認するための検査が完了した年月日
・当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
③下請契約に関する事項
・下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
・下請負人との契約日
・下請負人の商号、住所、許可番号
・建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
・当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
第四十条の四(国土交通大臣による調査等)
第40条の4 調査と報告について
第一項:調査の実施
国土交通大臣は、工事の契約が適切に行われているか、そして建設工事に携わる人がきちんと扱われているかを確認するために、建設業者に対して必要な調査を行います。この調査では、工事の契約状況や、特定の通知や話し合いがきちんと行われているか、下請けに対する適切な措置が実施されているかなど、国土交通省令で定められた様々な点を確認し、その結果を公表します。
第二項:調査結果の報告
国土交通大臣は、調査の結果を中央建設業審議会に報告します。
審議会から求められた場合は、国土交通大臣は、その調査内容について詳しく説明する義務があります。
第四十一条(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)
第41条 指導、助言、勧告
第一項:一般的な権限
国土交通大臣や都道府県知事は、建設業者や登録済みの建設業者団体に対して、適切な工事と業界の健全な発展のため、指導、助言、勧告を行う権限を持っています。
第二項:未払い賃金への対応
特定建設業者が元請けの工事で、下請け業者が労働者の賃金を遅延させた場合、国や都道府県は、元請けである特定建設業者に対して、未払い賃金を立て替えるなど適切な対応を勧告できます。
第三項:損害への対応
特定建設業者が元請けの工事で、下請けが工事中に他人に損害を与えた場合、国や都道府県は、元請けである特定建設業者に、損害額を立て替えるなど適切な対応を勧告できます。
第四十一条の二(建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)
第41条の2 建設資材製造業者等への勧告
第一項:違反の原因が資材にある場合の対応
国土交通大臣や都道府県知事が、建設業者または無許可で建設業を行う者に対して違反行為に関する指示を出すケースがあります。
違反の原因が工事に使われた建設資材にあると判断され、かつ、建設業者などへの指示だけでは再発防止が難しいと考えられる場合に、資材を提供した業者(製造・加工・輸入を行う者)にも対応を求めることができると定めています。
第二項:勧告に従わない場合の公表
国土交通大臣や都道府県知事が建設資材製造業者などに対して再発防止を勧告したにもかかわらず、それに従わない場合には、その事実を公表することができます。
第三項:命令の可能性
勧告を受けた資材業者が、正当な理由もなく対応しない場合に、その資材と同じ、またはよく似た資材が他の工事でも使われて問題が起こるおそれがあると判断されるときは、行政が対応を命じることができます。
第四項:報告徴収・立入検査
これらの勧告や命令を行うにあたって必要がある場合、行政は建設資材製造業者などに対して、業務に関する報告を求めたり、職員を現地に派遣して事務所や倉庫などを調査させたりすることができます。帳簿や物品の確認も可能です。
第五項:手続きの準用
立入検査については、すでに定められている他の条文(第二十六条の二十二第二項および第三項)の規定が準用され、同様の手続きが適用されます。
第四十二条(公正取引委員会への措置請求等)
第42条 公正取引委員会への措置
第一項
建設業者が建設業法の取引に関する規定に違反し、その行為が独占禁止法の「不公正な取引方法」にもあたると認められる場合、国土交通大臣や都道府県知事は、公正取引委員会に対して、その違反に対する対応をとるよう求めることができます。
第二項
また、元請業者と中小企業である下請業者との契約に関して、国土交通大臣や都道府県知事が公正取引委員会に対応を求めたときは、その事実を速やかに中小企業庁長官にも通知しなければならないとされています。
第四十二条の二(中小企業庁長官による措置)
第42条の2 中小企業庁長官による措置
第一項
中小企業庁長官は、下請の中小企業を守るために特に必要と認めた場合、元請や下請に対して取引内容の報告を求めたり、職員を営業所などに立ち入らせて帳簿や書類を調査させたりすることができます。
第二項
この立入検査については、すでに定められている他の立入検査のルール(第二十六条の二十二の二項・三項)を同じように適用します。
第三項
報告や検査の結果、元請が特定の条文に違反し、その内容が独占禁止法にも違反すると判断された場合は、公正取引委員会に対して対応を求めることができます。
第四項
第三項に基づいて公正取引委員会に対応を求めた場合には、速やかに、その元請に許可を出した国土交通大臣または都道府県知事に通知することが義務づけられています。
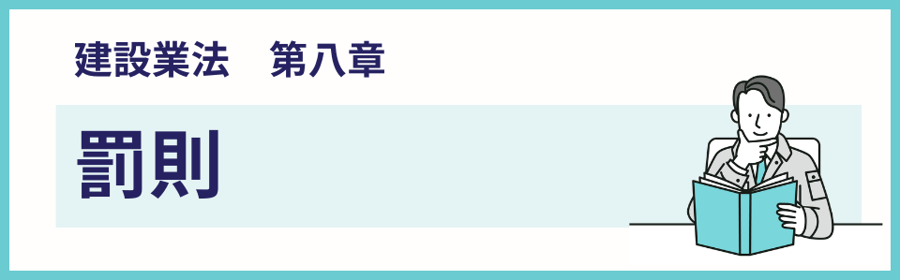
第四十六条(罰則)
第46条 贈賄に関する罰則
第一項
賄賂を実際に渡した人、渡そうと申し出た人、または渡すことを約束した人は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処されます。
第二項
ただし、この罪を犯した本人が自ら警察などに申し出た場合(自首)には、刑が軽くなったり、場合によっては免除されることもあります。
第四十七条(罰則)
第47条 建設業法違反の罰則
第一項
建設業法に違反した場合に科される罰則が定められています。次のいずれかの行為をした者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処されます。
①必要な許可を受けずに建設業を営んだ場合。
②特定建設業許可がないにも関わらず、元請業者となり、5,000万円(建築一式工事の場8,000万円)以上となる下請契約を締結した場合。
③営業停止処分を受けているにもかかわらず、建設業を営んだ場合。
④営業禁止処分を受けているにもかかわらず、建設業を営んだ場合。
⑤嘘の情報や不正な手段を用いて、建設業の許可や許可の更新をを受けた者。
第二項
これらの違反をした場合には、状況に応じて懲役と罰金の両方が科されることもあります。
第五十条(罰則)
第50条 虚偽申告等に関する罰則
この条文では、建設業法に定められた届出や申請において、不正や虚偽があった場合の罰則について規定しています。次のいずれかに当てはまる場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
①許可申請書や添付書類に虚偽の内容を記載して提出した場合。
②事業内容の変更届を提出しなかった場合、または虚偽の内容を記載して提出した場合
③許可基準をみたさなくなった旨の届出をしなかった場合。
④経営状況分析や経審の書類に虚偽の記載をして提出した場合。
これらの罪を犯した者に対しては、その状況(情状)に応じて、拘禁刑と罰金の両方を科すこともあります。
第五十二条(罰則)
第52条 建設業法における罰金刑
この条文では、建設業法で定められた重要な義務に違反した場合、100万円以下の罰金が科されることが規定されています。対象となる行為は次のとおりです。
①工事現場に必要な主任技術者や監理技術者を配置しなかった場合
②土木一式工事や建築一式工事に含まれる他の専門工事について、必要な対応を怠った場合
③建設業許可が失効した後、または許可取消処分・営業停止処分を受けた後に、必要な通知をしなかった場合
④登録経営状況分析機関や国土交通大臣・都道府県知事から求められた報告・資料提出を怠ったり、虚偽の資料を提出した場合
⑤国土交通大臣や都道府県知事から求められた業務報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合
⑥行政による立入検査を拒否・妨害したり、正当な理由なく検査から逃れた場合
⑦建設資材製造業者等が、資材に関する再発防止措置の命令を受けたにもかかわらず、従わなかった場合
第五十三条(罰則)
第53条 両罰規定について
この条文は、「両罰規定」と呼ばれるもので、違反行為を実際に行った従業者(法人の代表者や社員など)だけでなく、その法人自体にも罰金刑が科されることを定めています。
たとえば、無許可営業などの違反行為をした場合、違反者に対しては第四十七条の罰則が科せられますが、その法人に対しては最大1億円の罰金を科すことができると規定されています。
第五十五条(罰則)
第55条 過料が科されるケース
この条文では、刑事罰ほど重くはありませんが、10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される場合について定めています。対象となるのは、次のようなケースです。
◆廃業等の届け出を怠った場合
◆正当な理由がなく出頭の要求に応じなかった場合
◆標識を掲げていない場合
◆許可を受けた業者と誤認される表示をした場合
◆帳簿の備付けや保存を怠った場合