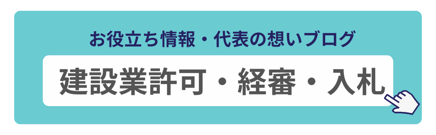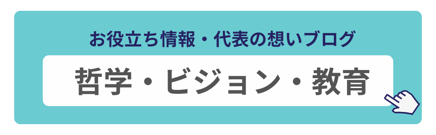・建設業会計の特長について
・完成工事高とは?
・完成工事高に含まれない売上とは?
・完成工事原価とは?
・完成工事総利益とは?
・完成工事未収入金とは?
・未成工事支出金とは?
・工事未払金とは?
・貸借対照表とは?
・貸借対照表で使用される勘定科目
・損益計算書とは?
・損益計算書で使用される勘定科目
・株主資本等変動計算書とは?
・なぜ必要なの?
・どの会社に必要?
・見るべきポイントは?
・個別注記表とは?
・なぜ必要なの?
・誰が作成するの?
・主な記載内容は?
・公開会社、非公開会社の違い

建設業会計の特長について
建設業の工事は、着工から完成までに長い時間がかかることが多いのが特徴です。そのため、売上を計上できるまでに時間がかかり、完成時にまとまった金額を計上するケースも少なくありません。一般的な会計は1年ごとに区切られますが、建設業では工事が1年以上に及ぶことも多いため、こうした事情に対応するために「建設業会計」という特有の会計方法が用いられています。建設業会計には、一般の会計ではあまり見られない独特の勘定科目もあります。
完成工事高とは?
完成工事高は、完成した工事に対する売上や収益を表す科目です。この完成工事高を計上する際には、主に次の2つの基準があります。
工事完成基準
工事がすべて完了し、発注者への引渡しが済んだ時点で売上を計上する方法です。
工事進行基準
工事の進み具合に合わせて、売上を少しずつ計上していく方法です。進捗の割合に応じて、その都度収益を認識します。
完成工事高に含まれない売上(兼業売上高)とは?
兼業売上高とは、建設業で定められた29業種に当てはまらない業務から得られる売上のことです。建設工事そのもの以外の業務による収入は「兼業による売上」として扱われ、完成工事高には含まれません。
兼業売上高に該当する主な業務例
◆造園関係:除草・草刈り・伐採・剪定・管理・造林 など
◆測量関係:測量・設計・地質調査・ボーリング など
◆保守関係:設備の保守・点検 など
◆清掃関係:清掃・浄化槽清掃・ボイラー洗浄・側溝清掃 など
◆維持管理関係:道路維持管理・造園の管理 など
◆宅建業務関係:建売住宅の建築・販売 など
◆運搬・販売関係:資材の運搬・販売・金属類の売却収入 など
◆機械関係:機械器具の製造・修理 など
◆除雪関係:除雪・融雪剤の散布 など
◆その他:人工出し(作業員の派遣)、自社物件の工事 など
完成工事原価とは?
完成工事原価とは、工事を完成させるために実際にかかった費用のことを指し、工事が終わった時点で費用として計上します。この原価は、大きく 「材料費・労務費・外注費・経費」 の4つに分けられます。
①材料費とは
工事のために直接購入した素材・半製品・製品、または材料貯蔵品から振り替えられた費用を指します(仮設材料の損耗額も含まれます)。実際に工事で使った分が材料費として計上され、未使用の分は「材料貯蔵品」として扱われます。
②労務費とは
現場で作業する直接雇用の作業員に支払う給料や手当などです。ただし、現場監督や事務員など、作業員以外の人件費は労務費ではなく「経費」として処理されます。
③外注費とは
他社と下請契約を結び、工事を依頼した際に支払う費用を外注費といいます。外注費は、外注先が就業時間や作業内容を管理し、それに対して報酬が支払われるものです。材料や道具を自社で準備して工事を依頼するケースや、人員不足で他社から応援を受ける場合などが含まれます。なお、請求書の大部分が人件費である場合は、「労務外注費」として分類されます。
④経費とは
材料費・労務費・外注費以外の工事に必要な費用です。主に次のような費用が含まれます。
動力用水光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務消耗品費、通信交通費、交際費、補償費、雑費 など。
また、現場代理人や施工管理など、労務費に該当しない従業員の人件費も経費に含まれます。これらは「うち人件費」として、給料・手当・退職金・法定福利費・福利厚生費に分けて記載します。さらに、これらの費用は工事への関わり方によって、次の2つに分類されます。
直接工事費
施工に直接かかる費用(例:材料費、作業員の賃金など)
間接工事費
施工を管理・サポートするためにかかる費用(例:現場管理費、事務経費など)
完成工事総利益とは?
工事で得た売上(完成工事高)から、その工事にかかった費用(完成工事原価)を引いたものです。差し引いてプラスなら「完成工事総利益」、マイナスなら「完成工事総損失」となります。
完成工事未収入金とは?
工事は終わって売上として計上したけれど、まだ入金されていない金額を指します。その後、代金を受け取ると現金や預金に振り替えられ、この勘定科目は0になります。
未成工事受入金とは?
工事がまだ完成していないのに、先に受け取っている請負代金のことです。工事が完成すると「完成工事高」として処理され、残高は0になります。
未成工事支出金とは?
工事がまだ終わっていない段階で発生した費用のうち、完成工事原価にまだ計上していないものです。
例:材料の購入代、下請け業者への前渡金や手付金など。
工事未払金とは?
工事にかかる費用(材料費・労務費・外注費・経費など)のうち、まだ支払っていない金額のことです。建設業における取引で発生した未払金であり、一般的な未払金(通信費や事務用品など)とは区別して扱われます。

貸借対照表とは?
貸借対照表は、会社の財務状況をひと目で表す報告書です。「どこからお金を集めているのか(負債・純資産)」と「そのお金をどのように使っているのか(資産)」を整理して示しています。ある時点での会社の安定性や支払い能力を判断する手がかりとなります。
貸借対照表で使用される勘定科目
①資産の部 流動資産
現金
会社ですぐに使えるお金のことです。紙幣・硬貨のほか、小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書なども含まれます。
預金
銀行や郵便局などに預けているお金のことです。
例:銀行預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金融信託など。
決算日から1年以内に現金化できるものは「預金」に区分されます。ただし、最初から1年以上現金化できないものは「投資その他の資産」に計上されることがあります。
受取手形
営業取引によって受け取った手形のことです。手形を割引いた場合や他人に譲渡した場合は、その金額を差し引いて注記します。また、破産・再生・更生などで、決算後1年以内に支払われないと明らかなものは「投資その他の資産」に区分されます。
有価証券
株式や債券など、時価の変動によって利益を得る目的で保有しているものです。また、決算期から1年以内に満期を迎える有価証券もここに含まれます。
材料貯蔵品
手元にある工事用の材料や消耗品、事務用の消耗品のうち、まだ未成工事支出金・完成工事原価・販売費及び一般管理費として使われていない分を指します。
短期貸付金
決算期から1年以内に返済される予定の貸付金のことです。ただし、当初から返済期限が1年以上の場合や、1年以上かかると見込まれる場合は「投資その他の資産(長期貸付金)」に計上されます。
前払費用
まだ発生していない費用を、あらかじめ支払ったお金のことです。
例:未経過の保険料、支払利息、賃借料など。
決算日から1年以内に費用となるものは「前払費用」として扱われ、1年を超えるものは「投資その他の資産(長期前払費用)」に計上されます。
繰延税金資産
将来にわたって、税金の負担が軽くなると見込まれる金額を資産として計上したものです。次のような場合が対象となります。
◆流動資産や流動負債に関係しているもの
◆特定の資産や負債には関係しないが、決算後1年以内に使われる見込みがあるもの
その他
完成工事未収入金以外の未収入金や、営業取引以外の取引によって生じた未収入金、営業外の受取手形など、決算期後1年以内に現金化できると見込まれるもので、他の流動資産の科目に当てはまらないものをいいます。分類が難しい資産のうち、近いうちに現金化される可能性のあるものがこの科目に含まれます。ただし、営業取引以外の取引によって生じたもののうち、当初の履行期が1年を超える、または超えると認められるものについては、「投資その他の資産」に記載することができます。
②資産の部 有形固定資産
建物
社屋や倉庫、車庫、工場、住宅などの建物本体と、それに付随する施設のことをいいます。
構築物
土地に固定された土木設備や工作物を指します。具体例としては門扉や看板、洗車ピットなどが含まれます。
機械装置
建設機械をはじめとするさまざまな機械や装置のことをいいます。
車両運搬具
重機やダンプ、営業車、発電機などの車両や運搬用の設備を指します。
工具器具
各種の工具や器具で、耐用年数が1年以上かつ取得価格が一定以上のものを指します。移動可能な仮設建物も含まれます。
備品
各種の備品で、耐用年数が1年以上かつ取得価格が一定以上のものをいいます。
土地
事業で使用する土地のことを指します。具体例としては、事業用の敷地や駐車場、資材置き場などがあります。
リース資産
ファイナンス・リース取引で貸主が所有する資産のうち、有形固定資産に該当するものを指します。具体例には建設機械やダンプ、営業車などがあります。
建設仮勘定
事業用固定資産の新設や増設にかかった支出を指します。具体的には、自社社屋の建設費や駐車場の造成費などが該当します。
③資産の部 無形固定資産
借地権
有償で取得した土地の使用権(地上権を含む)をいいます。たとえば、土地を借りてその上に事業用の建物を所有しているようなケースが該当します。
のれん
合併や事業譲渡で事業を取得した際に、取得原価が「取得した資産+引き受けた負債」の合計額を上回ったとき、その超過分を「のれん」といいます。いわば「目に見えない価値」であり、昔から使われる「のれん分け」という言葉にもあるように、信用やブランドといった形のない資産を表しています。
リース資産
ファイナンス・リース取引において借主側が使用する資産のうち、無形固定資産として扱われるものをいいます。具体的には、ソフトウェアの使用権を一定期間借り受けるような取引が該当し、リース契約に基づいて継続的に利用するケースなどが挙げられます。
④資産の部 投資その他の資産
投資有価証券
長期的に保有することを目的とした有価証券のことです。流動資産に含まれる短期保有の有価証券は除かれます。ただし、子会社や関連会社などの関係会社株式は含まれません。具体的には、国債や満期までの期間が1年以上ある債券、出資金などがこれに該当します。
関係会社株式・関係会社出資金
子会社や関連会社など、自社と資本関係や取引関係で深い結びつきのある会社に対して保有する株式や出資金のことです。どの会社が「子会社」「関連会社」にあたるかは法律などで定められています。
長期貸付金
決算日の翌日から1年を超えて返済される予定の貸付金をいいます。1年以内に返済されるものは「短期貸付金」として流動資産に計上されますが、それ以外の期間の長いものについては「長期貸付金」として固定資産に計上されます。
破産更生債権等
経営破綻や実質的に破綻状態にある債務者に対する債権のうち、決算期後1年以内に回収できないことが明らかなものです。具体的には、完成工事未収入金や受取手形といった営業債権、貸付金や立替金などのその他の債権の中で、破産債権、再生債権、更生債権などがこれに該当します。
長期前払費用
未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料などのうち、流動資産に計上される前払費用に該当しない、1年を超えて効果が及ぶ前払い費用をいいます。たとえば、自動車保険や火災保険の長期契約、複数年分をまとめて支払った事務所の賃貸料、長期のメンテナンス契約などの費用が該当します。これらのうち、決算日の翌日から1年を超えて費用となる部分が長期前払費用として扱われます。
繰延税金資産
税効果会計の適用により資産として計上される金額のうち、流動資産の繰延税金資産として記載されたもの以外のものをいいます。 損失や一時的な差異が発生したとき、将来の税金支払いを軽減できる見込みがある場合に計上されます。
⑤資産の部 繰延資産
創立費
会社を設立するときにかかる費用のことです。具体的には、定款や登記に関する書類の作成費用、認証手数料、設立登記のための登録免許税、株式募集のための広告費や印刷費などが含まれます。会社設立という一度きりの目的のために使う費用なので、繰延資産として処理されます。
開業費
会社設立後から実際に営業を始めるまでの準備にかかる費用のことです。具体的には、準備期間中の事務所賃借料や広告費、通信費、交通費、さらに開業前に購入した備品などが含まれます。
株式交付費
新株の発行や自己株式の処分に直接かかった費用のことです。具体的には、株式募集の広告費や金融機関への手数料、登記に関わる費用などが含まれます。
社債発行費
社債を発行する際に直接かかった費用をいいます。新株予約権の発行に関連する費用も含まれます。具体的には、社債募集の広告費や金融機関への取扱手数料、登記費用などが該当します。
開発費
新しい技術の導入、経営組織の改善、資源の開発、市場の開拓などにかかった費用のことです。将来の利益につながると期待される支出で、要件を満たせば資産として計上できます。ただし、毎年決まってかかるような通常の経費(経常費)は含まれません。
⑥負債の部 流動負債
支払手形
営業取引により発生した「手形での支払いの約束」をいいます。取引先に対し、手形に書かれた金額を期日に支払うことを約束したもので、実際に支払いが行われると手形債務は消滅します。
工事未払金
工事費に関する未払い分のことです。(工事原価に算入されるべき材料貯蔵品購入代金等を含みます。)ただし、税抜き方式を採用する場合でもこれらの取引にかかる消費税および地方消費税の額を含めて計上されます。
短期借入金
決算日から1年以内に返済予定の借入金のことです。金融手形も含まれます。銀行や金融機関、関連会社などからの短期借入残高が該当します。
リース債務
ファイナンス・リース取引に基づく債務のうち、決算期後1年以内に支払期限が到来するものをいいます。支払期限が1年以内のものは流動負債に、1年を超えるものは固定負債に分類されます。
未払金
営業取引以外の取引により生じた債務のうち、決算期後1年以内に支払期限が到来するものをいいます。広告宣伝費や事務用品の購入代金、固定資産の取得に関する未払いなどが該当します。
未払費用
継続的な契約に基づいてすでに役務が提供された分の未払い金額です。たとえば、未払給与手当や未払利息などが該当します。未払金は、商品やサービスなどの提供が終わっているのに対し、未払費用は継続的な契約の途中で計上する点が異なります。
未払法人税等
法人税、住民税、事業税などの未払い分です。決算時に合理的に見積もった納税額を「未払法人税等」として計上します。
預り金
会社が役員や従業員、取引先などから一時的に預かっているお金を指します。営業取引や営業外取引に基づき、1年以内に返済される、または返済見込みのあるものをいいます。
前受収益
前受利息や前受賃貸料などを指します。代金を先に受け取ったことで、将来商品やサービスを提供する義務が生じるため、負債として計上されます。
引当金
将来の支出や損失に備えてあらかじめ計上するお金のことです。
◆修繕引当金:完成した工事で使う機械などの修理に備えるもの。
◆完成工事補償引当金:引き渡した工事に不具合があった場合の補修や損害賠償、代金減額、契約解除などに備えるもの。
◆工事損失引当金:工事費用が収益を上回ると見込まれる場合に、その損失に備えるもの。
◆役員賞与引当金:決算後の株主総会で支給が決まる役員賞与に備えるもの。※すでに支払いが確定している場合は含みません。
⑦負債の部 固定負債
社債
会社が資金を集めるために発行する債券のことで、「事業債」とも呼ばれます。投資家などから直接お金を借りる方法であり、貸借対照表では負債として計上されます。なお、償還期限(返済期限)が1年以内に到来する場合は「流動負債」に分類されます。
長期借入金
決算日から1年を超えて返済する予定の借入金をいいます。銀行からの借入、役員や親会社からの借入、個人からの借入などが該当します。なお、1年以内に返済予定のものは「短期借入金」として流動負債に含めます。
リース債務
ファイナンス・リース取引によって発生する債務のうち、返済期限が決算終了後、1年を超えるものをいいます。これは「固定負債」に分類されます。一方で、1年以内に支払期限がくるものは「流動負債」として扱われます。
退職給与引当金
役員や従業員の退職金に備えて計上する引当金です。将来支払われる退職金のうち、現在までに発生していると見込まれる額をあらかじめ見積もって計上します。
負ののれん
合併や事業譲渡によって事業を取得した際、その取得原価が「取得資産-引き受け負債」の純額よりも少ない場合に生じる差額をいいます。主な原因として、簿外債務の存在や訴訟リスクなどが挙げられます。
⑧-1 純資産の部 株主資本
資本金
会社の運営に必要な元手となる資金のうち、株主や投資家からの出資金、または経営者の自己資金などをいいます。
新株式申込証拠金
申込期日経過後における新株式の申込証拠金をいいます。決算期末の時点で、まだ資本金に振り替えられていない場合には、資本金とは別の区分で計上されます。
資本準備金
会社設立時に払い込まれた資金のうち、資本金としては計上しなかった部分の累積額をいいます。将来、赤字が出たときなどに備えるための資金といえます。
その他資本剰余金
資本剰余金のうち、資本金や資本準備金の取り崩しで生じた剰余金や自己株式の処分差益など資本準備金以外のものをいいます。差益が出た場合は、その他資本剰余金は増加し、差損が出た場合は、その他資本剰余金は減少します。
利益準備金
会社法で定められた「法定準備金」の一つで、利益剰余金の一部を会社が積み立てておくものです。
繰越利益剰余金
これまでの利益の累積額を示します。複数年にわたる企業の経営成績を把握でき、企業の純資産の増加を反映します。長期的な成長や発展を支える大切な基盤となる資金です。
自己株式
会社が自ら保有している自社の発行済み株式をいいます。自己株式の買い戻しにより、資本構成の最適化を図ることができます。
⑧-2 純資産の部 評価・換算差額
繰延ヘッジ損益
繰延ヘッジ損益は、繰延ヘッジ処理が適用されるデリバティブ取引の評価替えで生じた差額から、税効果相当額を差し引いた金額をいいます。デリバティブとは、金利や為替、株価などの価格変動を基にした取引や金融商品を指します。
⑧-3 純資産の部
新株予約権
株式会社の株式を一定の条件のもとで取得できる権利です。新株予約権は、将来的な株主からの出資金となる可能性があるため、純資産に区分されます。

損益計算書とは?
損益計算書は、会社が 1年間でどれだけの収益を上げ、そのためにどれだけ費用を使ったのか をまとめた報告書です。「何にお金を使ったか」「どれだけ売上があったか」「最終的にどれくらい利益が残ったか」がひと目でわかります。建設業では特に 「完成工事高」「完成工事原価」「完成工事総利益」 といった勘定科目が使われます。
①売上高
完成工事高
工事が完成して、売上として計上された金額のことです。売上を認識するタイミングについては、一般的に「完成基準」が用いられますが、工期が長期にわたる工事では「進行基準」を使う場合もあります。
兼業事業売上高
建設業以外の事業(兼業事業)から得られる売上のことです。建設業法で定められた29業種に含まれない業務による収入が該当します。建設工事による売上ではなく、その他の事業による売上を「兼業事業売上高」として扱います。
②売上原価
完成工事原価
完成工事高(売上)に対応する工事の原価のことです。工事原価は、「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4つの要素で構成されています。
兼業事業売上原価
兼業事業売上高に対応する、兼業事業の原価のことです。兼業事業による売上がある場合は、その売上にかかった原価も損益計算書に記載する必要があります。
③総利益
売上総利益(売上総損失)
売上高から売上原価を引いた金額のことです。
◆売上高:商品やサービスの販売によって得た収入
◆売上原価:その商品やサービスを提供するためにかかった費用(売れた分に対応するもの)
完成工事総利益(完成工事総損失)
完成工事高から完成工事原価を引いた金額のことです。
◆完成工事高:工事によって得た売上
◆完成工事原価:その工事にかかった費用
つまり「完成工事総利益」とは、工事で得た売上からコストを差し引いた粗利益を指します。
兼業事業総利益(兼業事業総損失)
兼業事業売上高から兼業事業売上原価を差し引いた金額のことです。建設業を営む会社が、建設業以外の事業(兼業事業)も行っている場合、その兼業事業によって得た売上から、かかった費用を差し引いた粗利益を指します。
④販売費および一般管理費
役員報酬
取締役、執行役、会計参与、監査役などに支払われる報酬のことをいいます。役員賞与引当金繰入額も含まれます。ここでいう役員とは、従業員ではなく、会社の経営を担う立場にある人を指します。社内外を問わず、経営陣に支給される報酬は「役員報酬」として扱われ、支給の頻度に関わらず該当します。
従業員給料手当
営業や事務など、工事現場以外の業務に従事する従業員に支払う給料や手当をいいます。一方で、工事現場に直接携わる作業員などに支払う給料や手当は「完成工事原価」に含まれます。
退職金
役員や従業員に対して、退職時に支払われる金銭をいいます。退職年金掛金なども含まれます。なお、「退職給付に係る会計基準」を適用している場合は、退職金以外の退職給付費用などを適切な勘定科目に区分して記載します。
法定福利費
企業が法律に基づき、従業員のために負担する保険料などの費用をいいます。具体的には、健康保険・厚生年金保険・労働保険の事業主負担分や、児童手当拠出金などが含まれます。
修繕維持費
建物や機械などの固定資産を通常どおり使い続けるための維持管理や、壊れた部分を元に戻すためにかかる費用をいいます。具体的には、建物・機械・装置の修繕費や、倉庫内の物品を管理するための費用などが該当します。
事務用品費
事務作業に必要な消耗品や備品の購入にかかる費用をいいます。固定資産に含まれない事務用備品や、新聞・参考図書の購入費なども含まれます。たとえば、ノート、ボールペン、はさみ、ファイル、付箋、コピー用紙、封筒、名刺、出勤簿、納品書などが該当します。
通信交通費
業務に必要な通信や移動にかかる費用です。
◆通信費:電話代、データ通信料、郵便料金など
◆交通費:通勤定期代、業務移動の運賃やタクシー代など
◆旅費:出張に伴う交通費、高速料金、宿泊費、日当など
動力用水光熱費
事業に必要な電気・水道・ガスなどの費用です。電気料金、ガス料金、水道料金、冷暖房用の燃料費などが含まれます。
調査研究費
新製品や新技術の開発、既存製品の改良などにかかる費用をいいます。技術研究や開発に必要な人件費、材料費、設備費などが含まれます。
広告宣伝費
商品やサービスを広く知らせるための費用です。新聞・雑誌・テレビ・インターネット広告、ホームページ作成費用、屋外広告などが含まれます。
貸倒引当金繰入額
営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒引当金繰入額をいいます。貸倒損失が実際の損失額であるのに対して、貸倒引当金繰入はあくまでも見積りであるのが特徴です。
貸倒損失
営業取引に基づいて発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に対する貸倒損失をいいます。代表的な例として、取引先が倒産したり、債務超過に陥った場合に回収不能になるケースが挙げられます。
交際費
得意先、来客等の接待費、慶弔見舞及び中元歳暮品代等をいいます。支出した交際費のうち、損金として認められる範囲は限定されています。
寄付金
社会福祉団体等に対する寄付をいいます。寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が行った金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をいいます。
地代家賃
事務所、寮、社宅などの土地や建物を借りて使用するための費用をいいます。事業に必要な事務所や倉庫、店舗、駐車場などの賃料は、「地代家賃」として経費に計上されます。
減価償却費
建物や機械、車両などの固定資産について、時間の経過や使用により価値が減っていく分を費用として計上するものをいいます。資産の取得にかかった費用を一度に処理するのではなく、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費として計上していきます。
開発費償却
繰延資産として計上された開発費を、一定の期間にわたって費用として配分することをいいます。開発費の償却期間は原則として5年以内とされており、その期間内で計画的に償却していきます。
租税公課
事業所税、不動産取得税、固定資産税などの各種税金や、道路占用料、身体障害者雇用納付金といった公的な負担金をいいます。建設工事請負契約書に貼付する収入印紙も含まれます。なお、購入した印紙を保管している場合は、購入時に「租税公課」として処理し、決算時に未使用分があるときは「貯蔵品」として計上します。
保険料
災害補償などに備えるための損害保険料をいいます。具体的には、損害保険や法定外労災保険などが該当します。法人が役員や従業員を被保険者とする掛け捨て型の保険に加入し、その保険料を会社が負担した場合に用いられる科目です。
雑費
社内での打合せにかかる費用や、諸団体への会費など、他の販売費および一般管理費の科目に該当しない費用をいいます。分類が難しい少額の支出など、重要性が低いと判断される経費を処理する際に用いられる科目です。
営業利益(営業損失)
売上総利益(または売上総損失)から、販売費および一般管理費を差し引いた金額をいいます。建設業においては、完成工事高や兼業事業売上高から得られる利益を表し、いわゆる「本業による儲け」を示す指標です。
⑤営業外収益
受取利息
預金利息や、未収入金・貸付金などに対する利息をいいます。ただし、有価証券に関連する利息は含まれません。受取利息は収益ではありますが、本業とは直接関係しないため、営業外収益として計上されます。
有価証券利息
国債、地方債、社債などの公社債に対する利息をいいます。これらの利息収入は、有価証券に関連する収益として「営業外収益」に分類されます。
受取配当金
株式の保有によって得られる利益配当金をいいます。投資信託の収益分配金やみなし配当も含まれます。通常、配当金は源泉徴収されたうえで支払われるため、会計処理の際には控除された税金もあわせて計上します。
有価証券売却益
売買目的の株式、公社債等の売却による利益を含みます。売却し、売却価額が帳簿価額を上回った場合に、その差額を計上します。
雑収入
営業外収益のうち、他の科目に該当しない収入をいいます。具体的には、スクラップや廃材の売却による収入などが挙げられます。ただし、これらが事業目的の範囲内である場合には、「兼業売上高」として計上することもあります。
⑥営業外費用
支払利息
金融機関や他社からの借入金にかかる利息をいいます。たとえば、借入金の利息や社債の利息などが該当します。あくまで利息部分のみを指し、元本の返済額は含まれませんので、ご注意ください。
社債利息
企業が資金調達のために発行した社債や新株予約権付社債に対して支払う利息をいいます。社債を購入した社債権者へ利息を支払う際に使われる科目です。
貸倒引当金繰入額
営業以外の取引から生じた貸付金などの債権について、回収が困難になるおそれがある場合に、期末時点で債権の評価を行い、その見積もり額を貸倒引当金繰入額として計上するものです。
貸倒損失
営業以外の取引で生じた貸付金などの債権について、回収不能となった損失を指します。主な原因には、取引先の倒産や債務超過などが挙げられます。
創立費償却
繰延資産に計上された創立費のうち、一定期間にわたって分割して費用化する償却額をいいます。創立費は原則として5年間の均等償却が認められていますが、任意償却のため、一括償却することも可能です。
開業費償却
繰延資産に計上された開業費を一定期間に分けて費用計上する償却額を指します。開業費は原則として5年の均等償却が認められていますが、任意償却のため、各年度の償却額を自由に決めたり、一括償却することも可能です。
株式交付費償却
繰延資産に計上された株式交付費を、定められた期間内に分割して費用として計上する償却額をいいます。株式交付費は、新株発行や自己株式の処分にかかった費用であり、通常3年以内の期間で償却処理を行います。
社債発行費償却
繰延資産に計上された社債発行費を、一定期間にわたり分割して費用として計上する償却額を指します。社債は発行期間が年単位の場合が多いですが、長期債も存在します。実務では通常、3年を目安に償却処理を行います。
有価証券売却損
売買目的で保有している株式や公社債などを売却した際に生じた損失をいいます。売却価額が帳簿価額を下回った場合に「有価証券売却損」として計上され、逆に上回った場合は「有価証券売却益」として扱われます。
有価証券評価損
売買目的で保有している有価証券について、期末時点の時価が帳簿価額を下回る場合に計上する損失をいいます。
経常利益(経常損失)
営業利益(営業損失)に営業外収益の合計額を加え、営業外費用の合計額を差し引いた金額をいいます。経常利益は、企業が継続的にどれくらいの利益を上げているかを示す重要な指標のひとつです。
⑦特別利益
前期損益修正益
前期以前に計上された損益について、修正が必要となった場合に生じる利益をいいます。ただし、金額が重要でないものや、毎期繰り返し発生するようなものについては、経常利益に含めて処理することができます。
その他
固定資産売却益や投資有価証券売却益、財産受贈益など、通常の営業活動とは異なる臨時的な利益をいいます。ただし、金額が重要でないものや、毎期継続して発生するようなものについては、経常利益に含めて処理することができます。
⑧特別損失
前期損益修正損
前期以前に計上された損益について、誤りなどを修正することで生じた損失をいいます。ただし、金額が重要でないものや、毎期継続的に発生するようなものについては、経常損失として処理することができます。
その他
固定資産の売却損、減損損失、災害による損失、投資有価証券売却損、固定資産圧縮記帳損、損害賠償金など、通常の営業活動とは異なる異常な損失をいいます。ただし、金額が重要でないものや、毎期継続的に発生するものについては、経常損失として処理することができます。
⑨法人税等・当期純利益
税引前当期純利益(税引前当期純損失)
経常利益(または経常損失)に、特別利益と特別損失を加減して算出される金額をいいます。企業が1年間に得た利益から、法人税や住民税などの税金を除く、すべての収益と費用を反映した段階の利益です。
法人税、住民税及び事業税
その事業年度における税引前当期純利益に対して課される法人税等の金額をいいます。また、過年度分についての更正や決定により発生する納付税額や還付税額も含まれます。ここでいう「法人税等」には、法人税・住民税・利益に応じて課税される事業税が含まれます。
法人税等調整額
税効果会計の適用によって計上される法人税・住民税・事業税の調整額をいいます。
会社の「会計上の利益」と「税務上の課税所得」には一時的な差異が生じることがあるため、その差異を将来の税金に反映させる目的で調整を行います。
当期純利益(当期純損失)
税引前当期純利益(税引前当期純損失)から法人税・住民税・事業税を差し引き、法人税等調整額を加減して算出される金額をいいます。
これは一定期間における会社の最終的な利益(または損失)を示し、企業の経営成績を評価するうえで最も基本的かつ重要な指標とされています。

株主資本等変動計算書とは?
会社の「資本金」や「剰余金」など、純資産の増減とその理由を示す財務書類です。以前は貸借対照表の注記で示されていましたが、よりわかりやすく整理された形で独立した書類として作成されるようになりました。
なぜ必要なのか
会社法の改正により、株主総会などの決定によって、資本金や剰余金の額が柔軟に変えられるようになりました。その変動を分かりやすく伝えるために、この計算書が導入されました。
どの会社に必要?
すべての会社に作成義務があります。合資会社や合同会社などでは「社員資本等変動計算書」という名称になります。
見るべきポイント
表の中で特に重要なのは次の3つです。
◆当期首残高:期首時点の純資産の残高
◆当期変動額合計:期中に増減した金額の合計
◆当期末残高:期末時点での残高(貸借対照表の純資産と一致)
これらを確認することで、純資産が「どう動いたか」「なぜ動いたか」が把握できます。

個別注記表とは?
個別注記表は、貸借対照表や損益計算書などの決算書だけでは伝えきれない情報を補足する書類です。企業の財務内容や経営方針などを、より正確に理解してもらうために作成されます。
なぜ必要なのか
決算書だけでは、会社の会計方針の考え方や、特別な取引の影響などが見えにくいことがあります。そのため、注記という形で背景や理由を説明することで、より信頼性の高い情報提供が可能になります。
誰が作成するのか
すべての株式会社が作成する必要があります。ただし、会社の規模や株式の公開・非公開により、記載が必要な項目は異なります。
主な記載内容
個別注記表には、最大で19項目の注記を行います。代表的な内容は以下の通りです。
◆会計方針(資産評価方法、減価償却の方法など)
◆表示方法や会計方針を変更した場合の理由
◆決算書の誤りの訂正内容
◆配当の内容や株式の変動状況
◆関連会社や親子会社との取引
◆収益の認識方法に関する情報 など
※すべての会社で必ず記載が求められる項目も一部あります。
公開会社と非公開会社の違い
公開会社(株式を自由に譲渡できる会社)は、多くの項目について注記が必要です。非公開会社(株式の譲渡に制限がある会社)は、一部の注記が省略できます。
個別注記表は、決算書だけでは読み取れない企業の実態を明らかにする重要な資料です。特に、投資家や金融機関などの関係者にとって、企業の信頼性を判断するうえで欠かせない情報源となります。