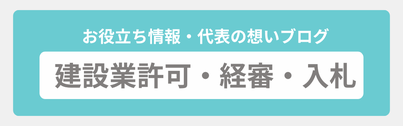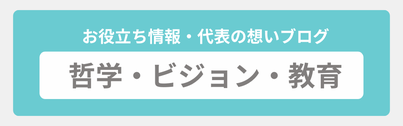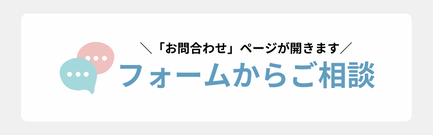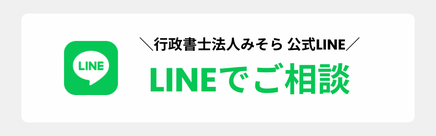建設業法においては、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するため建設業許可やそれに伴う技術者の制度が設けられています。建設業許可業者となるための基本的な要件は次の4つです。
(1)経営能力
(2)財産的基礎
(3)技術力
(4)適格性

建設業許可業者は、工事現場における施工所技術上の管理をつかさどる者として主任技術者、特定建設工事の場合は監理技術者を配置しなければなりません。
また配置される工事が、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、請負金額が4,000万円、建築一式の場合は8,000万円以上となる場合には、対象となる現場専任となります。
現場専任となると、その工事期間に他の工事の配置技術者になることができません。たとえ建設業許可が不要である軽微な工事、請負金額100万円の現場であってもです。
ただし令和2年10月に施行された改正建設業法により、監理技術者の配置義務が緩和されました。
当面は2つの現場に限られますが、監理技術者のもとに監理技術者”補佐”をおいた場合には、1名の監理技術者が専任が求められる2つの現場を兼務できます。監理技術者補佐は1級施工管理技士検定の一次に合格した者が対象になります。1次に合格をした方は技士補とも呼ばれます。
この技術検定についても、令和3年度から実務経験年数が緩和されています。2級施工管理技士に合格しているものは、実務経験を経ることなく1級の1次を受験することができるようになりました。
また1級の二次についても、監理技術者のもとで実務経験2年以上、または専任の主任技術者として実務経験1年以上が経過すると受験資格が得られます。

先ほどの「2現場兼務のための監理技術者補佐」として2年が経過すれば、そのかたが1級の2次検定を受験することができます。検定と実務経験のタイミングによりますが、2級の1次を受け始めてからおおよそ4~5年後ぐらいには、監理技術者となれる道が開けている、と考えてよいのではないでしょうか?
さて、建設業許可業者は、請負契約の内容を技術的観点から確認し、適正な契約の締結および履行の確保を担う技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
こちらは”営業所の専任技術者”と呼ばれているものです。
現場専任の主任技術者、監理技術者と混同しないように注意したいものです。
比較的規模の小さい建設業許可業者は、営業所の専任技術者が現場を見なければとても回らない状況になることが多々あります。
私もお客様からよくご相談をいただきます。
これについては、平成15年に通知文章(一部省略)が出ています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあるものについては、営業所の専任技術者が現場の主任技術者または監理技術者となった場合でも、営業所に常勤して専らその職務に従事しているものとして扱う。
(平成15年4月21日国総建第18号)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
つまり、会社と現場がすぐに行き来できる場所にあれば兼務が可能です。会社と現場との距離、所要時間については、発注者の見解を確認した上で判断をしたほうが安全です。私見ですが、クルマで30分~1時間程度が目安ではないかと思います。
ただし4,000万円(建築一式8,000万円)以上の専任を要する工事のときは営業所専任技術者との兼務はできません。
このように、営業所の専任技術者が現場の配置技術者になることができるケースは限られていますので、慎重な現場の運用が必要です。
※令和6年7月、以下は追加で記載します。
令和6年6月の国会で建設業法等の改正案(新担い手3法)が可決成立しました。
この法案には、営業所専任技術者が現場の配置技術者となれる要件の緩和も含まれています。
緩和するうえでの条件はざっくりと次のとおりです。
1.兼任する現場と現場の移動が容易
2.ICTを活用し遠隔からの現場の確認が可能
3.兼任する現場数は一定以下
4.政令で定める請負金額以下の工事を対象とする(請負金額は今後、決められる)
営業所専任技術者(許可のために必要な1名)の現場兼任、現場の配置技術者の兼任、
ともに可能となり、人手不足対策の有効な改正だと思います。
ただし、カメラによる監視や建設キャリアアップシステムを使った施工体制の確など
ITシステムを活用することが条件づけられています。
※下記は過去の国交省の資料です。
イメージをつかむ参考資料としてください(政令で定める請負金額は2024.7現在は未定です)

お問い合わせ
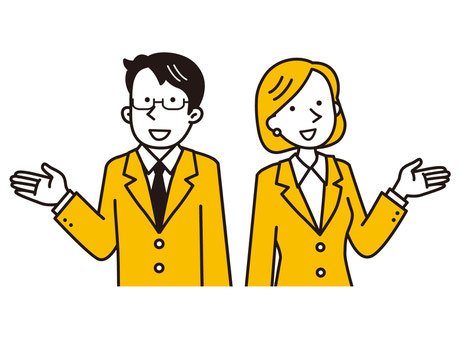
みそらでは建設業許可や経審はもちろん「建設キャリアアップシステム代行申請」など、建設業者様の事業に関わる申請業務を代行しております。申請業務に関わる事務作業の負担軽減はお任せください。